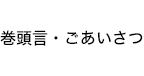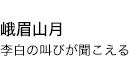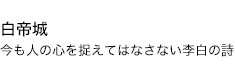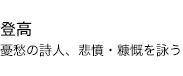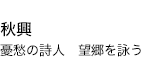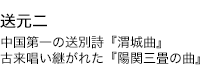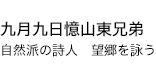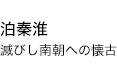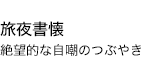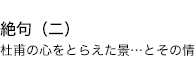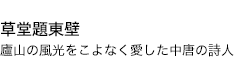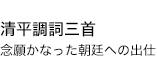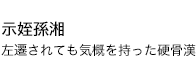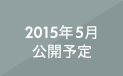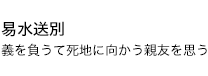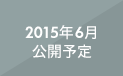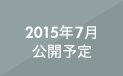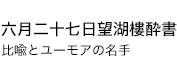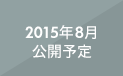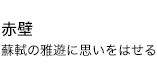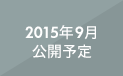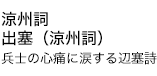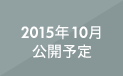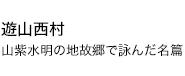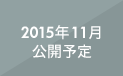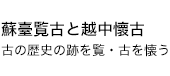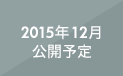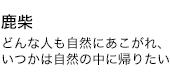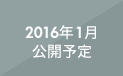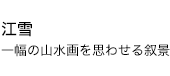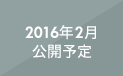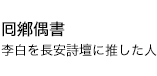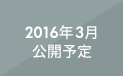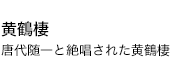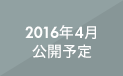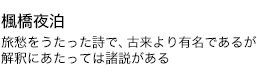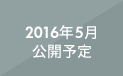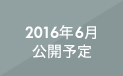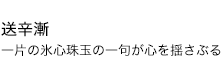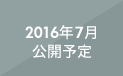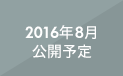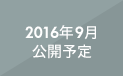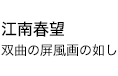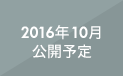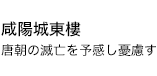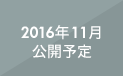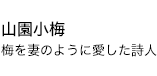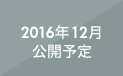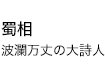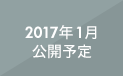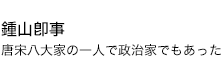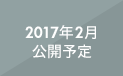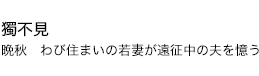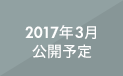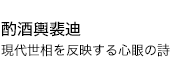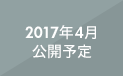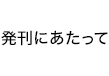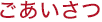
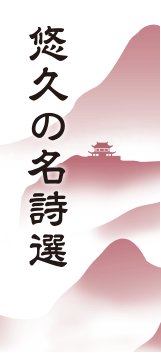 公益社団法人 関西吟詩文化協会 総本部
公益社団法人 関西吟詩文化協会 総本部
会長 山口華雋
巻頭言の一節に「………其の意を悟り其の義を楽しむにいたりて完きなり。楽しめば則生ず、詩中の景、詩中の情、油然として其の心に生じて来りて、己遂に詩中の人となる。これを同化という。吟詩の妙味ここにあり、修養の道も亦ここにあり。」があります。
中国から伝わり日本の文化に大きな影響を与えた漢詩、又、漢字からやがてひらがなが生まれ、日本固有の短歌の世界が花開き、やがて俳句・新体詩が生まれてまいりました。私達は、この伝統文化である漢詩・和歌・俳句・新体詩を愛唱することにより、又、作詩を楽しむことにより、人生の修養を図らんとするものであります。
其の意を悟り、その義を楽しむには、教本の紙面での解説では、不十分であることから、詩の背景・作者の心情などを詳しく解説する詳解書の発行が嘱望されておりましたが(星野哲史先生・藤元哲湊先生らによる詳解書あり)総本部では、平成十七年に、より吟詠をたのしんで頂く一助として、機関誌「吟詩日本」に「悠久の名詩」として漢詩・作者をより詳しく紹介することといたし、現在まで連載して参りました。
この度創立八十周年を迎えるに当たり、記念事業の一環として、過去掲載された悠久の名詩シリーズを一冊の書籍にまとめました。日頃の吟詠活動及び、より有意義な詩吟人生をお送り戴く為の資料のひとつとしてご愛読下されば幸甚にぞんじます。
| ▲このページの先頭へ |