漢詩紹介
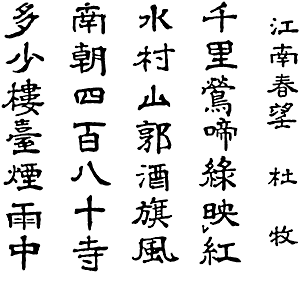
CD①収録 吟者:曾根鷺夕
2014年5月掲載
読み方
- 江南春望<杜牧>
- 千里鶯啼いて 緑紅に映ず
- 水村山郭 酒旗の風
- 南朝 四百八十寺
- 多少の楼台 煙雨の中
- こうなんしゅんぼう<とぼく>
- せんりうぐいすないて みどりくれないに えいず
- すいそんさんかく しゅきのかぜ
- なんちょう しひゃくはちじゅうじ
- たしょうのろうだい えんうのうち
詩の意味
江南地方には春が千里四方に満ちていて、いたる所で鶯(うぐいす)が鳴き、緑の若葉は赤い花に映りあってまことに美しい。水辺の村にも山あいの村にも、酒屋の旗が春風(はるかぜ)にひらめいているのが見える。
思えばあの南朝のころには仏教が盛んで、この地にも480もの寺院が建てられていたというが、今もなお多くの楼台がその名残(なごり)をとどめ、煙るような霧雨の中に聳(そび)え立っているのがあちらこちらに見える。
鑑賞
晴れても降ってもよく、昔も今もよい江南地方
多くの詩集には「江南の春」とあります。千里・水村・山郭で広大な田園風景が浮かび、そして緑・紅(くれない)・白(酒旗)からは彩り豊かな絵を見るようです。加えて鶯の声にそよ風と、視覚・聴覚・触覚すべての感覚を動員して春景色を描いています。さらに春雨(はるさめ)に煙る、南朝時代の寺院群の眺めは、時を忘れて作者の心をなごませています。
語句の意味
-
- 江南春望
- 揚子江下流の江南地方の春の眺め
-
- 山 郭
- 山あいの村
-
- 酒旗風
- 酒屋の目印(めじるし)の旗が風になびく
-
- 南 朝
- 3世紀から6世紀にかけて今の南京に都を置いた呉・東晋・宋・斉・梁・陳の六つの王朝をいう 仏教が盛んだった
-
- 多 少
- 多くの
-
- 煙 雨
- 霧雨(きりさめ)
詩の形
仄(そく)起こり七言絶句(しちごんぜっく)の形であって、上平声(じょうひょうしょう)一東韻の紅、風、中の字が使われている。仄起こりとは起句の二番目の字が仄字である場合をいうのである。 右にこの詩の平字仄字の関係を明記しておくので、よく吟味して作詩の参考にしてください。なお転句の八十寺は下三連なので、唐宋以降の詩詞中にはハッシンジと平声に読むこともある。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
杜 牧 803-852
晩唐の政治家・詩人
京兆(けいちょう=今の西安)の名門の家に生まれ、若いころから詩文が得意で、23歳の時「阿房宮の賦」(あぼうきゅうのふ)を作り、その天才ぶりが世に知れ渡った。26歳で進士となり、江蘇省の楊州に赴任した時代には名作を多く残している。杜牧は美男子で歌舞を好み色好みで通っていたから、艶っぽい詩が多いけれど、半面その人柄は剛直で正義感に富み、大胆に天下国家を論じたりもした。33歳の時、中央政府の役人になるが、弟が眼病を患っていたので、弟思いの杜牧は自ら報酬の高い地方官を願い出て面倒を見た話はまた別の一面を語っている。
