漢詩紹介
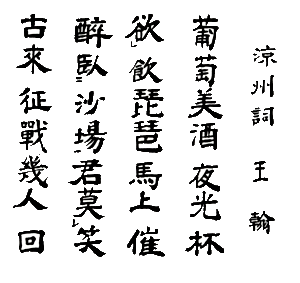
CD①収録 吟者:大取鷲照
2014年8月掲載
読み方
- 涼州の詩<王翰>
- 葡萄の美酒 夜光の杯
- 飲まんと欲して琵琶 馬上に催す
- 酔うて沙場に臥す 君笑う莫れ
- 古来征戦 幾人か回る
- りょうしゅうのし<おうかん>
- ぶどうのびしゅ やこうのさかずき
- のまんとほっして びわ ばじょうに もよおす
- ようて しゃじょうにふす きみ わろうなかれ
- こらいせいせん いくにんか かえる
詩の意味
涼州の地に駐屯した出征兵士にとっては、名物の葡萄のうま酒を、月の光に照らされる杯で飲むのがもっとも趣きがある。今、それを飲もうとすれば、馬上でかき鳴らす琵琶の調べが酒杯を促すようである。
今、戦(いくさ)に出ようとするこの砂漠に酔い臥すことがあっても、人々よ笑わないでほしい。昔から遠く西域への戦にかり出された人たちの中で、幾人が無事に故郷に帰ることができただろうか。
鑑賞
初唐七言絶句の第一と評される悲壮な詩
西北の国境へ行って守備をする兵士の胸のうち、「明日は死ぬかも知れない身であり、せめてつかの間のなぐさめだ。飲んだり歌ったりの酔態は、許してやって、どうぞ笑わないでほしい」と、国の役人である作者が同情しているのです。
語句の意味
-
- 葡萄美酒
- 西域地方産の最高級のブドウ酒
-
- 夜光杯
- 西域地方名産の白玉(はくぎょく=大理石の一種)で作った杯 それ自体が光を受けて透明に光る部分が夜の光を感じさせる
-
- 琵 琶
- 木製の弦楽器で胴に柄があり四弦(五弦もある) 胴はなすび形で平たい 起源はペルシャ・アラビアとされインド・西域・中国を経て奈良時代に我が国に伝来した ここでは胡地特有の馬上の楽器
-
- 催
- (杯を干せと)うながすように (琵琶を)かきならす
-
- 沙 場
- (戦場である)砂漠
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十灰(かい)韻の杯、催、回の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
王 翰 687-726
初唐から盛唐の政治家・詩人
山西省太原?の人。幼少時代から優れた才能の持ち主であったが、それにうぬぼれて、酒を好み馬を飼い、女性や楽士を集めて宴会や狩猟にふけった。24歳で進士に及第し順調に出世していたが行動に問題が多く、その後南方に左遷され、その地で死んだ。詩人としては名声を得、特に国境地帯の兵士を歌った辺塞詩に特色がある。享年40歳。
