漢詩紹介
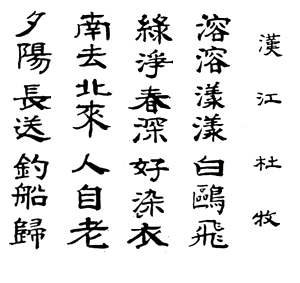
CD2収録 吟者:松尾佳恵
2014年12月掲載
読み方
- 漢江<杜牧>
- 溶溶漾漾として 白鷗飛び
- 綠浄く春深くして 好く衣を染む
- 南去北来 人自ずから老い
- 夕陽長く送る 釣船の帰るを
- かんこう<とぼく>
- ようよう ようようとして はくおうとび
- みどりきよく はるふかくして よくころもをそむ
- なんきょ ほくらい ひとおのずからおい
- せきよう ながくおくる ちょうせんのかえるを
詩の意味
豊かな漢江の水はさかんに波立ち流れて、その上を白い鷗が飛んでいる。春景色もようやく深まり、美しい緑色の流れは衣を染めたいくらいである。
(しかし世の人はこの好景にも心を留める様子もなく)南へ北へと忙しく往来して、心のゆとりもなく老いてゆくようであり、人生の哀歓を感じる。ふと見ると西に傾いた太陽の光の影は長く、釣りから帰る船を送っている。
語句の意味
-
- 漢 江
- 川の名 陝西(せんせい)省寧羌(ねいきょう)県に発し湖北省の漢口(かんこう)で揚子江にそそぐ
-
- 溶 溶
- 豊かな水のさかんに流れるさま
-
- 漾 漾
- 水の波立ち動くさま
-
- 緑 浄
- 緑色の水が美しく澄み切っている
-
- 南去北来
- 南北に往来して忙しく暮らす
鑑賞
老いゆくは我が身なりけり
晩年の作者が漢江に臨んで己をふり返っている。前半2句は大らかで美しい。ゆったりと波打つ川面(かわも)あたりは春の真っ盛り。白い鷗の〝白〟に川の〝緑〟も鮮やかで、ついこの詩は当時の明るく雄大な漢江のさまを歌っていると思われがちである。そうではない。つまり転句から急に語調が下降する。忙しい生活を営みつつ人は老いてゆくと嘆きが始まるのである。そして老人が乗っているであろう釣り船に己の人生を投影させている。その漁翁は不変の自然の営みに埋没している人なのか、あるいは世俗に無頓着で孤高を保っている人なのかは読者の想像に委ねられる。いずれにしても老境に向かう己の嘆きを歌っている。
参考
唐代文学上の区分について
唐詩は文学史上通例、初唐・盛唐・中唐・晩唐の4つに区分される。その境界線には諸説がある。
①初唐(618~711の約90年間) 唐の初めから玄宗即位の前年まで。近体詩の確立前期。陳子昂(ちんすごう)・杜審言(としんげん)・宋之問(そうしもん)ら。
②盛唐(712~765の約50年間) 玄宗の治世から代宗の時代まで。近体詩の絶頂期。安禄山の乱を中に含む。杜甫・李白・王維・孟浩然・高適(こうせき)・岑参(しんしん)・王昌齢ら。
③中唐(766~835の約70年間) 代宗から文宗時代まで。近体詩の減速時代。古文復興運動が盛んになった。張継・柳宗元・韓愈・白居易ら。
④晩唐(836~906の約60年間) 唐時代の終わりまで。近体詩の低迷期。杜牧・李商隠(りしょういん)ら。
詩の形
この詩の構造は平起こり七言絶句の形であって、上平声五微の韻の飛、衣、歸の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
杜 牧 803-852
晩唐の政治家・詩人
号は樊川(はんせん)。京兆(けいちょう=今の西安)の名門の家に生まれ、若いころから詩文が得意で、23歳の時「阿房宮の賦」(あぼうきゅうのふ)を作り、その天才ぶりが世に知れ渡った。26歳で進士となり、江蘇省の楊州に赴任した時代には名作を多く残している。杜牧は美男子で歌舞を好み青楼に浮名(うきな)を流したこともあった。艶っぽい詩が多いけれど、半面その人柄は剛直で正義感に富み、大胆に天下国家を論じたりもした。33歳の時、中央政府の役人になるが、弟が眼病を患っていたので、弟思いの杜牧は自ら報酬の高い地方官を願い出て面倒を見た話はまた別の一面を語っている。中書舎人(ちゅうしょしゃじん)となって没す。享年50。「樊川文集」20巻、「樊川詩集」7巻がある。
