漢詩紹介
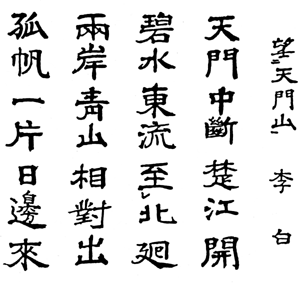
吟者:松浦 菖帑
2004年9月掲載
読み方
- 天門山を望む <李 白>
- 天門中断して 楚江開け
- 碧水東に流れて 北に至りて廻る
- 両岸の青山 相対して出で
- 孤帆一片 日辺より来る
- てんもんざんをのぞむ <りはく>
- てんもんちゅうだんして そこうひらけ
- へきすいひがしにながれて きたにいたりてめぐる
- りょうがんのせいざん あいたいしていで
- こはんいっぺん にちへんよりきたる
詩の意味
天門山は真ん中から断ち切られて、その間を楚江が流れている。ここで深みどりの川は東の方に流れて、さらに北に向きを変えて流れている。
両岸には青々とした山が向き合って突き出しており、その切れ目の奥の方から一艘の舟が下って来るのは、まるで太陽の沈むあたりから流れ下って来るかのようである。
語句の意味
-
- 天門山
- 今の安徽省当塗県(あんきしょうとうとけん)の西南の蕪湖(ぶこ)のあたりにある山で東梁山(とうりょうざん)と西梁山の二つの山は揚子江(長江)を挟んで向かい合いその形があたかも天の門のようになっているところから名づけられた
-
- 楚 江
- 揚子江 このあたりは春秋時代から楚国と呼ばれていたのでこの名がある
-
- 碧 水
- 深みどりの川
鑑賞
中国の雄大な景色を描いた神技の傑作
この名称の山は中国には幾か所もある。ここでは作者が安徽省から揚子江を南東に下る途中、舟中から天門山を望んで作られたもの。年代は不明だが50歳ごろかとも。一・二句で聳え立つ両山と大空を、さらに滔々たる大河のうねり流れるさまを描き、三句目でやおら目を転じて彼方上流を眺めると帆かけ船が小さな影となって下って来る図は、遠近法の効果を最大に利かせ、雄大な自然を余すところなく描いている。つまり大叙景詩である。
胡応麟(こおうりん)という昔の学者は「この詩および『早発白帝城』などはともに自然を最高に表現している。まことに神技の作品といえる」と絶賛している。
漢詩の小知識
日辺と長安ではどちらが近いか
晋(しん)の明帝(みんてい)がまだ幼かったころ長安から来た使者の前で「長安と日辺ではどちらが遠いかね」と父の元帝(げんてい)が質問したところ幼帝が「長安が近い。未だかつて日辺(太陽)から来た人を見たことがないから」と答えた。翌日同じ質問をしたところ「日辺が近い。頭をあげると太陽は見えますが長安は見えないから」と答えた。この話は幼帝の聡明さを示すものとなっている。それなりの理を述べて面白い話である。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十灰(かい)韻の開、廻、来の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
李 白 701~762
盛唐時代の詩人
四川省の青蓮郷(せいれんきょう)の人といわれるが出生には謎が多い。若いころ任侠の徒と交わったり、隠者のように山にこもったりの暮らしを送っていた。25歳ごろ故国を離れ漂泊しながら42歳で長安に赴いた。天才的詩才が玄宗皇帝にも知られ、2年間は帝の側近にあったが、豪放な性格から追放され再び各地を漂泊した。安禄山の乱後では反皇帝派に立ったため囚われ流罪(るざい)となったがのち赦され、長江を下る旅の途上で亡くなったといわれている。あまりの自由奔放・変幻自在の性格や詩風のためか、世の人は李白のことを「詩仙」と称えている。酒と月を愛した。享年62。
