漢詩紹介
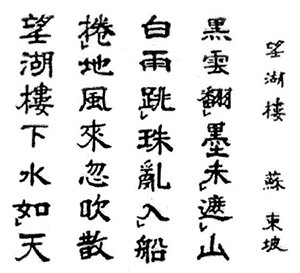
読み方
- 望湖楼 <蘇東坡>
- 黒雲 墨を翻して 未だ山を遮らず
- 白雨 珠を跳らして 乱れて船に入る
- 地を捲くの風は来りて 忽ち吹き散ず
- 望湖楼下 水天の如し
- ぼうころう <そとうば>
- こくうん すみをひるがえして いまだやまをさえぎらず
- はくう たまをおどらして みだれてふねにいる
- ちをまくのかぜはきたりて たちまちふきさんず
- ぼうころうか みずてんのごとし
詩の意味
まっ黒な雲が墨をぶちまけたように、むらむらと広がってゆくが、その雲がまだ前方の山を隠してしまわないうちに、早くも夕立の大粒の雨が玉を跳らせたように、乱れて船の中に降り注いできた。
と見る間に、大地を巻き上げるような強い風が吹いて来て、たちまちこの雨雲を吹き散らしてしまった。そしてそのあとには何事もなかったかのように望湖楼下の西湖の水は、澄み渡った大空のように再び静まりかえっている。
語句の意味
-
- 望湖楼
- 浙江省杭州の鳳凰山にあって西湖を見おろす高殿
-
- 翻 墨
- 墨汁をひっくり返したような
-
- 白 雨
- 激しいにわか雨 すなわち夕立
-
- 跳 珠
- 白い宝石をまき散らすさま
鑑賞
夕立を詠った最高傑作
楼上で一杯やりながらの作である。真黒い雲に大粒の雨、そして激しい風。それらが具体的に描写してあるので迫力はもちろん恐怖すら与える。しかも一・二句の「黒雲」と「白雨」、「翻墨」と「跳珠」の対語を用いることで天候の急変が視覚的にもリズミカルに伝えられる。大風の描写もいささか誇張であろうが、暗雲を吹き散らすさまは映像を見るようで鮮明である。黒雲が起こって湖が静まるまで数十分は経ているだろうが、異様な空模様を早送りのコマのように数分間の現象に思わせる言葉選びは緊張感や迫力を増幅させる。リズムとしては三句までは2・2・3で運ばれ、結句だけは4・3の調べでトーンダウンしている。楽曲における変調のように、動から静の世界に字数によっても誘い込むのも傑作といわれる所以(ゆえん)である。
備考
本題は「六月二十七日望湖楼酔書五絶」であるが、本会では「望湖楼」と簡略にした。作者37歳の作である。役人として杭州の通判(地方都市の監督官 宋代に設けられた)の時、高楼で詠んだ。見下ろしている西湖は今も名勝地で、周囲は15キロメートル。国賓館や貴人の別荘などが多く点在する。
漢詩の小知識
通韻について
詩には一定の句末に同韻の字を用いて音調を整える法則がある。これを押韻という。韻とは、漢字をその韻母にあたる部分によって106種に分けたもの。普通押韻には一種類の韻しか用いられないが、ほかの韻と通用することができる。これを通韻という。たとえば上平声一韻の東(とう)に属する字と上平声二韻の冬(とう)に属する字は共通して押韻してもかまわないことになっている。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十五刪(さん)韻の山と下平声一先(せん)韻の船、天とが通韻して使われている。
平仄
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
蘇東坡 1036~1101
北宋の政治家・詩人・文章家
名は軾(しょく)、字は子贍(しせん)、号は東坡。四川省眉山県の生まれ。父洵(じゅん)、弟轍(てつ)とともに「唐宋八大家」に数えられ、三蘇といわれた名文章家。幼にして 道教的教育を受け、20歳の時上京して官途に就く。当時の礼部侍郎(れいぶじろう)であった欧陽修に見出され、終世師と仰ぐ。中央、地方の官を歴任しその間たびたび流謫(るたく)された。 官は礼部尚書(れいぶしょうしょ=今の文部科学大臣)に至る。江蘇省常州において没す。散文「赤壁の賦(せきへきのふ)」は有名。死後皇帝より文忠公と諡(おくりな)された。享年65。
