漢詩紹介
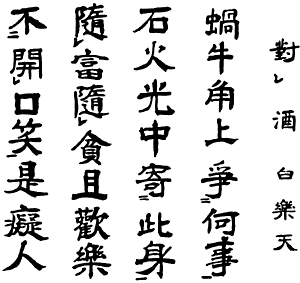
CD①収録 吟者:稲田菖胤
2014年5月掲載
読み方
- 酒に対す <白 居易>
- 蝸牛角上 何事を争う
- 石火光中 此の身を寄す
- 富に随い貧に随うて 且く歓楽す
- 口を開いて笑わざるは 是痴人
- さけにたいす <はく きょい>
- かぎゅうかくじょう なにごとをあらそう
- せっかこうちゅう このみをよす
- とみにしたがいひんにしたごオて しばらくかんらくす
- くちをひらいてわらわざるは これちじん
詩の意味
かたつむりの角の上のような小さな世界で人々は何を争っているのか。あたかも火打石の火花のような一瞬のはかないこの世の中に、仮にこの身を置いているというのに。
金持ちであろうと貧しかろうと、それなりに楽しく暮らそう。口をあけて気持ちよく笑わないのは、愚かな人である。
語句の意味
-
- 蝸牛角上争
- かたつむりの角の上での争い とるに足らない争い
-
- 石 火
- 火打石を打つ時に出る火花 ほんの短い時間 人生のはかないたとえ
-
- 且
- ほんのわずかな間
-
- 痴 人
- 愚か者
鑑賞
笑う門には福来たる
58歳のころの作品である。当時、洛陽に隠棲(いんせい)していた。起句は「荘子(そうじ)」の「蝸(かたつむり)の左角に国する者あり、触氏(しょくし)という。蝸の右角に国する者あり、蛮氏(ばんし)という。時に相ともに地を争って戦い、死するもの数万人……」に基づく。また結句も「荘子」の「人上寿は百歳、中寿は八十、下寿は六十、病痩(びょうそう)・死喪(しそう)・憂患(ゆうかん)を除きて、その中に口を開きて笑うもの一月の中、四五日に過ぎざるのみ」とあるの借用か。
白居易の人生指針は「知足安分」、つまり足るを知り、分に安んじることである。であるのに世間では無意味な争いが続き人々は悲しんでいる。富める人も貧しいものも楽しい人生でなくてはならない。はかない人生の中で笑う日の1日でも多いことが人生の幸せであると歌うのである。それにしても、はかない人生を「石火」と言い切ったのは究極すぎて面白い。日本古典では「露」「朝顔」「霜」「浮雲」などにたとえられるが、その比類ではない短時間表現である。もしかして人生の無常観は中国の方が先覚かもしれない。
漢詩の小知識
「荘子」とはどんな本
戦国時代に荘子(そうし)が著したとされる思想書。33編。その中心思想は、すべての相対的価値を否定する「万物斉同」論である。この世にはもともと生死・美醜・強弱・賢愚・大小などの相対的対立はないのに人が勝手に評価しているだけ。だから戦争や苦悩が始まる。その相対的対立が消滅したところに「道」がある。その「道」を求めるというのである。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十一真(しん)韻の身、人の字が使われている。起句は踏み落としである。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
白居易 772~846
中唐の政治家・大詩人
名は居易、字は楽天、号は香山居士。陝西省渭南(せんせいしょう いなん)の人(太原の人ともいう)。家は代々官吏であった。早くから詩を作り、16歳で「春草の詩」、17歳で「王昭君」の作がある。貞元16年(800)の進士。同期の進士、元稹(げんしん)と深い親交があった。江西省九江の司馬に左遷されたこともあるが、ほぼ中央の官にあり、晩年は刑部(けいぶ)尚書(法務大臣の格)にて没す。享年75。「長恨歌」「琵琶行」の大作を残す。「白氏長慶集」「白氏文集(もんじゅう)」等が我が国にも伝わり、平安文学に感化影響を与えた。
