漢詩紹介
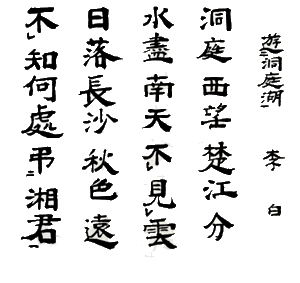
吟者:辰巳快水
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 洞庭湖に遊ぶ <李白>
- 洞庭西に望めば 楚江分かる
- 水尽きて南天 雲を見ず
- 日 落ちて 長沙 秋色遠し
- 知らず 何れの処にか 湘君を弔わん
- どうていこにあそぶ <りはく>
- どうていにしにのぞめば そこうわかる
- みずつきてなんてん くもをみず
- ひ おちて ちょうさ しゅうしょくとおし
- しらず いずれのところにか しょうくんをとむらわん
詩の意味
洞庭湖から西方を望めば、楚江が分流して湖に入っている。湖水が尽きるところ(水平線)、南の空には一点の雲もなく晴れわたっている。
やがて日は落ちて、長沙の方は、秋に色づいた陸地が遠く見えている。ただ広々としていて、悲劇の女神である湘君をどこで(どの方角に)弔ってよいかわからない。
語句の意味
-
- 洞庭湖
- 揚子江中流にある中国第一の湖 広さと景観は雄大を極める
-
- 楚 江
- 長江をこの地方では楚江と呼ぶ 洞庭湖に注ぐ
-
- 長 沙
- 洞庭湖の南100㎞にある 今の湖南省の都 楚江の支流である湘江の東岸にある
-
- 湘 君
- 伝説時代(紀元前3000年ごろ)の帝王堯(ぎょう)の娘 姉を娥皇(がこう)妹を女英(じょえい)といいともに舜帝に嫁した 舜が国内巡視中蒼梧(そうご)で没すると二妃(にき)とも湘水に身を投げた 二人を湘君といい湖水の神として崇めている 洞庭湖北西端の君山に湘君の祠がある
鑑賞
スケールの大きい叙景から懐古へ
洞庭湖を遊覧した時の詩で、5首連作の第1首である。前半は西に南に頭を巡らして、実際には見えないが「楚江分る」「水尽き」と言って、想像も含めて渺々(びょうびょう)たる洞庭湖のスケールの大きさを実感させる。洞庭湖といっても雨季と乾季では面積が変わる。雨季は最長南北130㎞、幅100㎞ともなる。後半は「日落長沙」「湘君」など歴史上の語句を用い、過去にスポットを当て、懐古詩で終わっている。つまり李白たちは湖上から雄大な光景を眺めながら、3000年前、舜帝に殉死した悲運の湘君を偲んでいる。
悲運と言えば今船に乗る3人も左遷されたり流罪(るざい)の身であったりして、決して幸運な者たちではないからこそ、湘君が浮かんだのかもしれない。後半二句は空想の世界である。洞庭湖からいくらなんでも100㎞離れた長沙の町が見えるわけがない。長沙まで足を運ぶことのできない李白らは、何としてもここで両妃の悲運を弔いたかったのであろう。
備考
この詩の本題は「族叔刑部侍郎曄(ぞくしゅくけいぶじろうよう)及び中書賈舎人至(ちゅうしょかしゃじんし)に陪(ばい)し洞庭に遊ぶ」であるが、本会では「洞庭湖に遊ぶ」と簡略にした。李白が夜郎(やろう)に流された後、赦免の報に接し、東に向かう途次、やはり左遷の身であった知人の李曄と賈至とともに湖に船を浮かべていた759年ごろ、作者59歳ごろの作とされている。
参考
堯帝と舜帝とは
伝説時代の帝王の名。五帝(伝説上の聖天子)のうち四番目の堯と、五番目の舜。両者とも儒家では理想の聖天子として称えられ、孔子も「論語」の中で尊崇している。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十二文(ぶん)韻の分、雲、君の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
李 白 701~762
盛唐時代の詩人
四川省の青蓮郷(せいれんきょう)の人といわれるが出生には謎が多い。若いころ任侠の徒と交わったり、隠者のように山にこもったりの暮らしを送っていた。25歳ごろ故国を離れ漂泊しながら42歳で長安に赴いた。天才的詩才が玄宗皇帝にも知られ、2年間は帝の側近にあったが、豪放な性格から追放され、再び漂泊した。安禄山の乱後では反朝廷側に立ったため囚われ流罪となったがのち赦され、長江を下る旅の途上で亡くなったといわれている。あまりの自由奔放・変幻自在の性格や詩風のためか、世の人は「詩仙」と称えている。酒と月を愛した。享年62。
