漢詩紹介
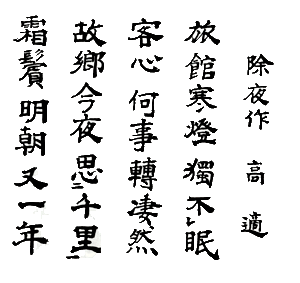
吟者:松野春秀
2010年12月掲載
読み方
- 除夜の作 <高 適>
- 旅館の寒灯 独り眠らず
- 客心何事ぞ 転凄然
- 故郷今夜 千里を思う
- 霜鬢明朝 又一年
- じょやのさく <こう せき>
- りょかんのかんとう ひとりねむらず
- かくしんなにごとぞ うたたせいぜん
- こきょうこんや せんりをおもオ
- そうびんみょうちょう またいちねん
詩の意味
旅館の寒々とした物わびしい灯火のもと、私は独り眠られない夜を過ごしている。旅人の心はどうしてこのように一層さびしさを感じるのであろうか。
故郷の家族の者たちは、きっと大晦日の今夜、遠くを旅している私のことを思ってくれているだろう。明日の朝、元旦になれば、この白い鬢面(びんめん)のわが身は、また一つ年齢を加えなければならないのだ。
語句の意味
-
- 除 夜
- 大晦日の夜 一説によると作者49歳の除夜
-
- 客 心
- 旅人の心情 ここでは作者の心
-
- 何 事
- どうして
-
- 凄 然
- 寂しく悲しい
-
- 思千里
- 故郷の人々が千里のかなたにある私を思う
-
- 霜 鬢
- 霜が降りたような白髪の増えた鬢
鑑賞
賑やかな故郷の家族と孤独な旅人
旅にあって迎えた大晦日の夜の感慨である。一読して、新年を迎えるにあたり、すでに老境の自分がまた一つ年を取ることへのさみしさが読み取れる。中国では今でも、年が明けると一歳加わるのである。
前半二句では、旅の途中の独り寝に愁いの募ってくるさまを客観的に歌い上げ、後半二句において、その愁いの内容を物語る。前半後半とも対句をなし、その淡々とした歌い口は、旅愁のうら哀しさを表現するのに非常に効果的である。
「寒灯」の「寒」は寒々とした、の意味だけではなく、わびしく、ものさみしい、の情感を持たせるのが良い。旅館というのも安宿の貧相な部屋が連想される。地方へ赴任した折の作であろう。
なお、転句は本会のように「故郷の家族が旅人の自分を思ってくれる」という解釈と「自分が故郷の家族を思う」という二説があるが、後者は平凡で、やはり前者の方が作者の孤独感を一層引き立て、望郷の念をかき立てる。
参考
髙適は河南省開封市に祀(まつ)られている。「三賢祠(さんけんし)」と呼ばれるその社(やしろ)は李白、杜甫、髙適の三詩人が共に旅をした場所である。
髙適は一篇を吟ずるごとに好事家(こうじか)の伝えるところとなった。晩年に始めた作詩がその素晴らしさでたちまち世間に有名になったというエピソードがある。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声一先(せん)韻の眠、然、年の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
髙 適 702?~765
盛唐の政治家・詩人
山東省浜州(ひんしゅう)の人。字は達夫(たっぷ)また仲武。若いころは不遇で貧しかったが、科挙に合格して、その後安禄山の乱のとき認められ出世コースに乗った。天宝3年(744)杜甫、李白と相知り、50歳ごろから作詩を始めた。辺塞詩人として有名。生涯の多くを軍隊生活で過ごしたためと豪壮にして節義を重んじた性格を反映して、詩にも気骨があり重厚である。「髙古豪壮(気高く古風で雅であり勢いが盛ん)」と評されている。「高常侍集」10巻がある。
