漢詩紹介
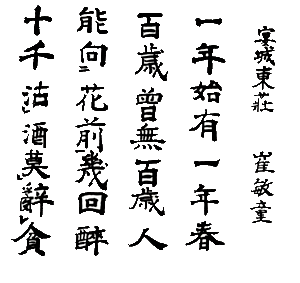
吟者:原 江龍
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 城東の荘に宴す <崔敏童>
- 一年始めて有り 一年の春
- 百歳曽て無し 百歳の人
- 能く花前に向かって 幾回か酔う
- 十千 酒を沽うて 貧を辞する莫れ
- じょうとうのそうにえんす <さいびんどう>
- いちねんはじめてあり いちねんのはる
- ひゃくさいかつてなし ひゃくさいのひと
- よくかぜんにむかって いくかいかよオ
- じゅうせん さけをこオて ひんをじするなかれ
詩の意味
一年が終われば新しい年の春がおとずれてくれる。(春はこのように永遠に巡ってくるが)人間の寿命は百歳といわれるけれど、百歳まで生きた人は今まで一人もいない。
このように咲く花の前でお互いに酒を飲んで、いったい生涯のうちに何度酔うことができるだろうか。そう幾度もあるまい。(だから今日一日は存分に飲もう) 一万銭で酒を買ってこいよ。金がないとか貧相なことは口にしないでくれ。
語句の意味
-
- 城東荘
- 作者の従兄(いとこ=また兄、弟の説もある)の崔恵童が王維の輞川荘(もうせんそう)の対岸に建てた別荘で長安の東郊にあった玉山草堂
-
- 百 歳
- 人の寿命の上限 「荘子(そうじ)盗跖篇(とうせきへん)」に「人の上寿は百歳 中寿は八十 下寿は六十……」とある
-
- 十 千
- 千銭の十倍 美酒斗十千といって高価な酒
-
- 沽
- 買う
鑑賞
酒こそ人生の花
前二句が対句になっており、語調もよく分かりやすい。なかなか磊落(らいらく)な詩である。酔いしれることのできる日は人生でそうあるものではない、とは「荘子」の「下寿は六十」に続き「病痩・死哀・憂患を除けば 其の中 口を開いて笑うは一月のうち 四、五日に過ぎざるのみ」に基づく。財布のことは気にせず酒を買ってこいという。こういう捨て身の酒への向かい方は、多くの詩にある。
「曲江」(杜甫)には「毎日江頭酔いを尽くして帰る」と。李白の長詩「将進酒(しょうしんしゅ)」にも「斗酒十千 歓謔(かんぎゃく)を恣(ほし)いままにする 主人何為(なんす)れぞ銭少なしと言わんや 径(ただ)ちに須らく沽酒して君に対して飲むべし 五花の馬 千金の裘(ふくろ) 児を呼んで将(も)ち出だして美酒に換え 爾(なんじ)と同じく銷(しょう)せん 万古の憂い」(お金がないなど言うな、馬でも上等の皮袋でも質に入れて酒に換えてこい。それで万古の憂いを癒そう)と。泥酔状態の李白が浮かぶ。さらに同じく李白の名文に「……浮生(ふせい)は夢の如し。歓を為すこと幾何(いくばく)ぞ。古人燭(しょく)を秉(と)りて夜遊ぶ、良(まこと)に以(ゆえ)有るなり。……」とある。「酒」という字はないが、昔の人は灯火のもとで夜まで酒を飲んで歓楽を尽くしたというではないか、もっともなことだ、と豪語している。同根同趣である。
備考
ともに宴に臨んだ兄弟が唱和した詩
「唐詩選」にはこの詩に続けて、兄と思われる崔恵童の「奉和宴城東荘」というのがある。兄弟が同席した折の作品といわれているが、兄が弟に「奉和」の字を用いるのはあり得ないので、身分のある人に奉った詩であるとか、敏童が兄で恵童が弟であるとか、また「奉和」の二字は後世の人が付け加えたのだろうなど考証の定まらない詩である。しかしそれらを無視して、兄弟が宴席で作りあったと見れば、一脈通じるところがある。
一月 主人 笑うこと幾回ぞ 主人=恵童
相逢い相値(う)う 且(しばら)く杯を銜(ふく)まん 値=会う
眼のあたりに看る 春色 流水の如きを 銜=ふくむ
今日の残花は 昨日開きしなり
なお、本会では「唐詩選」を出典としているが、他の詩集には「一年始→一年又」「花前→花間」「貧→頻」などの字句の異同がある。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十一真(しん)韻の春、人、貧の字が使われている。なお転句は挟み平となっている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
崔敏童 正没年不詳
初唐(盛唐とも)の役人・詩人
河南博州、今の山東省東昌府の人。役人生活をしたと思われるが、その任地や役職など、全く不明である。一族に崔恵童という人がいるが、兄なのか、師なのかも不明。従弟(いとこ)だという本もある。
