漢詩紹介
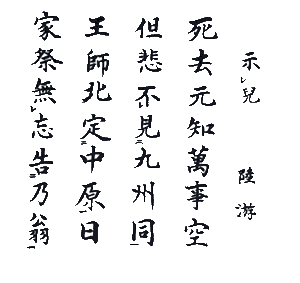
吟者:中島 菖豊
2005年4月掲載
読み方
- 児に示す <陸游>
- 死去すれば元知る 万事空しと
- 但悲しむ 九州の 同じきを見ざるを
- 王師北のかた 中原を定むるの日
- 家祭忘るる無かれ 乃翁に告ぐるを
- じにしめす <りくゆう>
- しきょすればもとしる ばんじむなしと
- ただかなしむ きゅうしゅうの おなじきをみざるを
- おうしきたのかた ちゅうげんをさだむるのひ
- かさいわするるなかれ だいおうにつぐるを
詩の意味
死んでしまえば万事が空しくなってしまうと、かねてから知りぬいてはいる。それでも天下が統一されるのをこの目で見ずに終わるのが、悲しくてならない。
やがて我が宋国帝王の軍隊が北に進んで、中原(ちゅうげん)の地を平定した日には、我が家の先祖の祀(まつ)りをし、この父の霊に報告するのを忘れてはならぬぞ。
語句の意味
-
- 九州同
- 中国全土の統一 「九州」は古代中国全土を九つの区域に分けていた伝説による呼び名
-
- 王 師
- 朝廷の軍隊
-
- 中 原
- 中国中央部の黄河流域の一帯
-
- 乃 翁
- 汝の翁 おまえの父 ここでは陸游をさす 「乃」はなんじ
鑑賞
愛国の至情に燃える作者辞世の詩
宋が再び強国になることを叫び続けたにもかかわらず国勢が傾き、これからの運命が気にかかり、子供たちに与えた遺言詩である。表面的な詩意は「九州」「王師」「中原」「乃翁」の熟語さえわかればほぼ理解できるが、やはりこの詩も、当時の歴史を知らなければ真相に近づけない。1200年代と言えば宋が北方からの異民族「金」によって追われ、止む無く南方の臨安に(今の杭州)に臨時政府を置いた屈辱の時代である。しかも南宋では暗君が多数続き、奸臣(かんしん)が政権を握るなどしたため、加えてモンゴル民族の南下もあって、国勢は傾き始めていた。愛国の情熱き作者はすでに80歳に近かったが、政府の弱腰に切歯扼腕(せっしやくわん)していたので、死んでも死にきれない思いで見つめていた。このままでは漢民族の宋が中国大陸を健全な形で復権する日は、夢で見るしかないのである。仮にその日が来たら、すでにあの世にいる自分に喜びの報告をしてほしいと、子供らに託すのである。淡々とした歌い方であるが、85歳の切望感を味わいたい。
参考
宋国の滅亡
宋国が滅びるのを嘆く詩は、本会では謝枋得(しゃほうとく)の「妻子良友に別る」や文天祥の「零丁洋を過ぐ」が代表であるが、これらは陸游から70年後のことである。南宋はモンゴル民族の「元」によって1279年に滅ぼされた。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声一東(とう)韻の空、同、翁の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
陸 游 1124~1209
南宋前期の政治家・詩人
号は放翁。浙江省紹興の人。20歳で結婚したが間もなく離婚。29歳のとき科挙に首席で合格したが、ある人の恨みを買って殿試(最終選考試験)で落第した。5年後ようやく官職に就いた。各地の任地を回り、65歳以降はほぼ故郷で作詞にふけった。その間詩人として名をあげ南宋四大家の随一とされる。32歳から85歳の死に至るまで50年間の詩作「剣南詩稿」85巻を遺した。特に晩年は多作で、総数1万首近くある。愛国の詩人として北方平定を願っていたが果たされなかった。享年85。
