漢詩紹介
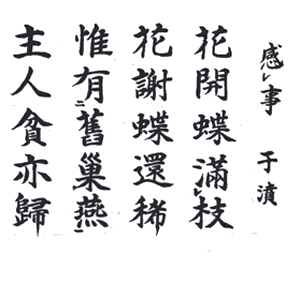
吟者:原 江龍
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 事に感ず <于 濆>
- 花開けば 蝶枝に満つ
- 花謝すれば 蝶還稀なり
- 惟 旧巣の 燕有りて
- 主人 貧しきも 亦帰る
- ことにかんず <う ふん>
- はなひらけば ちょうえだにみつ
- はなしゃすれば ちょうまたまれなり
- ただ きゅうそうの つばめありて
- しゅじん まずしきも またかえる
詩の意味
花が開くとこれを慕って蝶が枝に集まるが、花が散ってしまうと蝶が来ることも稀である。
ただ去年の燕が古巣を忘れず、主人が貧乏であるにもかかわらず、今年もまた帰ってくれたことは、実にうれしいことだ。
語句の意味
-
- 花 謝
- 花が散る
-
- 旧 巣
- 古い巣
鑑賞
思いのままに生きる蝶や燕
季節は春から夏の初めにかけて、住まいの近くで見た光景であろう。蝶は甘い蜜のある花に集まるが、花が散るとどこかに去っていく。それに対し燕は、住み心地の良さを感じたら、その家の貧富にかかわらず翌年も同じ所に巣を作る。小動物の自然のままに生きるさまを見たままに詩にした素朴さがいい。こういう素朴な詩は日本にも数多くある。蛙が土の中から顔を出したとか、赤とんぼが稲穂の上を飛びまわるとか、メダカが春の小川で泳ぎ始めるとか、その観察のさり気無さが人を引き付ける。一方で脚色家である世人が、これに色をつける鑑賞もある。すなわちこの詩は蝶と燕を引用して、人の心を風刺したもので、花を富貴な人に、蝶を軽薄な者にたとえ、燕は邪心のない人情の持ち主になぞらえる。両者とも鑑賞は可能だが、蝶も燕も脚色せず、あるがままに生きている自然界の描写として収まらないか。
備考
この詩の作者は于瀆(うとく)なる人物ではないか
「唐才子伝」の唐備の項に「于瀆には花に対して言う、『花開きて蝶は枝に満つ、花謝して蝶の来ること稀なり。惟旧巣の燕有り、主人貧にして亦帰る』などの詩がある。これは軽薄な時俗(じぞく)のために発せられたもので、人々の戒めとしている」とある。「濆」と「瀆」の字形が似ているので後世誤ったとも考えられる。したがって作者は于瀆なる人物という説もある。
漢詩の小知識
漢詩作成の規則
一首の中に同一漢字は用いないというのがある。しかし有名詩人の中にもこの規則を無視して敢えて同一漢字を用いているものがあるのでその優劣は言えないが、この詩も「花」「蝶」が二度使われている。
詩の形
平起こり五言絶句の形であって、上平声五微(び)韻の稀、帰の字と上平声四支(し)韻の枝が通韻として使われている。また五言詩の場合、一句目は押韻しなくてもよいのに枝が押韻されている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
于 濆 生没年不詳
晩唐の役人・詩人
生卒年も出生地もわからない。名は濆、字は子漪(しい)。晩唐懿宗(いそう)の咸通(かんつう)2年(861)に進士にあげられたが、安徽省泗州の判官(地方の属官)に終わった。詩は巧みであったが、時流を喜ばず、声律に拘束されて軽薄になるのを嫌い、社会の矛盾を直截(ちょくせつ)的に訴える詩が多い。古風30篇を作り、自ら逸詩と称した。「于濆詩集」1巻がある。
