漢詩紹介
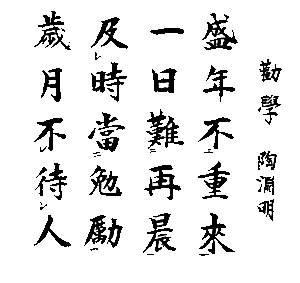
吟者:鈴木 永山
2005年8月掲載
読み方
- 勧 学 <陶淵明>
- 盛年 重ねて来らず
- 一日 再び晨なり難し
- 時に及んで 当に勉励すべし
- 歳月は 人を待たず
- かんがく <とうえんめい>
- せいねん かさねてきたらず
- いちじつ ふたたびあしたなりがたし
- ときにおよんで まさにべんれいすべし
- さいげつは ひとをまたず
詩の意味
若くて血気盛んな年頃は再び来ないし、一日のうちの朝も二度と来ない。
それゆえに、学ぶべき時によく努め励んで充分に勉強しておかなければならない。歳月は人を待つものではないから、いつの間にか過ぎ去ってしまうのである。
語句の意味
-
- 盛 年
- 血気盛んな年頃 壮年
-
- 晨
- 朝
-
- 時
- ……するのに適する時
-
- 当
- ……するのが当然だ 再読文字
-
- 勉 励
- 努め励む
鑑賞
教訓好きの日本人が選び取った名詩
原詩の「雑詩」が述べるところは、人生は不変で、塵のようにはかなく、舞い落ちたところで親しい人を作っていくのだから、そこで歓びを得たなら、みんなで酒を囲んで大いに楽しもうではないか。その機会を逃さず充実した時を過ごしたいものだ、となる。ところが後4句が切り離されて、若い時は2度とないからその時こそ勉学に励むべしと、勉学の教訓詩として定着した。それは作者の意図する方向とは別のものである。作者は、詩と酒を友として自然の中で生活することこそ人生の本質と見つけ、動乱が繰り返される不安定な世相において乱世を憂いつつ田園の超俗を求めるという道を選んだ。教訓好きの日本人が学問のすすめとして借用したものであろう。
ところが一般的にはこの4句を1絶句と見ることに慣れているので、今では学問を励ます教訓詩となっていることに違和感はない。1句1句に重みがあって実にいい。どの句も座右の銘にしたいくらいの名言である。
備考
この詩の原題は12句からなる五言古詩「雑詩」で、最後の4句を取り出したものである。全部で12首作っているが、これはそのうちの1首で、晩年の作品であろう。淵明の詩は李白、杜甫をはじめ多くの詩人達に影響を与えた。しかし彼の生きた時代には評価されなかった。300年を経て淵明の詩は孟浩然に受け継がれて花開き、その名声を不動の地位に押しあげたのは、まぎれもなく王維であった。淵明が生きた350年後のことであった。
雑 詩(12首の1)
- 人生無根帶
- 人生根帶(こんたい)無く
- 飄如陌上塵
- 飄(ひょう)として陌上(はくじょう)の塵のごとし
- 分散逐風転
- 分散して風を逐(お)うて転じ
- 此已非常身
- 此れ已(すで)に常の身に非(あら)ず
- 落地為兄弟
- 地に落ちて兄弟(けいてい)と為る
- 何必骨肉親
- 何ぞ必ずしも骨肉の親(しん)のみならんや
- 得歓当作楽
- 歓(かん)を得(う)れば当(まさ)に楽しみを作(な)すべく
- 斗酒聚比隣
- 斗酒比隣を聚(あつ)めん
- 盛年不重来
- 一日難再晨
- 及時当勉励
- 歳月不待人
詩の形
五言12句の古詩の最後の4句である。上平声十一真(しん)韻の晨、人の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
陶淵明 365~427
六(りく)朝時代の東晋の詩人
潯陽(じんよう=江西省九江市)に生まれる。名は潜(せん)、字を淵明・元亮という。南朝時代の代表的詩人で、30歳代を挟んで13年間の役人生活をしたが、405(40歳)年には官を辞して故郷に帰り、自ら鍬(くわ)を持って田畑を耕す生活を送ったので、世に田園詩人と言われる。酒を好み酒にまつわる詩が多い。庭に5本の柳を植えていたので五柳先生ともいわれた。享年64。没後世の人々から靖節(せいせつ)先生と諡(おくりな)された。
