漢詩紹介
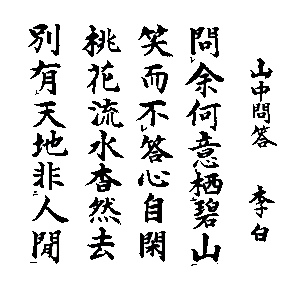
CD④収録 吟者:岸本快伸
2016年2月掲載
読み方
- 山中問答 <李 白>
- 余に問う何の意ぞ 碧山に栖むと
- 笑って答えず 心自ずから閑なり
- 桃花流水 杳然として去り
- 別に天地の 人間に非ざる有り
- さんちゅうもんどう <りはく>
- よにとオなんのいぞ へきざんにすむと
- わらってこたえず こころおのずからかんなり
- とうかりゅうすい ようぜんとしてさり
- べつにてんちの じんかんにあらざるあり
詩の意味
人が私にたずねる。「どういうつもりで人里離れた緑の山にこもっているのか」。そういう問いには笑っているだけで答えず、わが心はのどかである。
桃の花びらが、川の流れの中に散り、はるかかなたへ流れてゆく。ここは世俗と違う、素晴らしい世界が別に開かれているのさ。
語句の意味
-
- 何 意
- どういうつもりで
-
- 碧 山
- 清澄な感じの強いふかみどりの山
-
- 桃花流水
- 桃の花びらが水に浮かんで流れ去る 陶淵明の「桃花源の記」をふまえている
-
- 杳 然
- はるかに奥深いさま 遠いようす
-
- 人 間
- 人間世界 俗世間
鑑賞
華麗な宮廷生活にも孤高の世界にも浸る仙人李白
俗世間にこだわらず、ゆったりとした世界に棲んでいる心境を詠じた詩で、作者53歳のころと言われている。つまり玄宗に長安を追われて10年後、長江流域を放浪していたころとなる。安禄山の乱の余波で捕囚となる2年前である。10年前は玄宗と楊貴妃の前にあって、二人を華やかに詠った「清平調詞」の詩風からすれば別人の興である。「詩仙」とはこういう多面性をとらえた名なのかもしれない。
さて離俗の心を詠った詩は中国には多い。同じ李白に「山中幽人と対酌す」があるし、李白が下敷きにしたと言われる陶淵明の長詩「飲酒」の一節「廬(いおり)を結んで人境に在り 而(しか)も車馬の喧(かまびす)しき無し 君に問う何ぞ能く爾(しか)ると 心遠ければ地自ら偏なり(中略) 此の中に真意有り 弁ぜんと欲して已(すで)に言を忘る」などはその最たるものであろう。結局この離俗の心は俗人にはわからないというのだから現代人もただ想像するしかないのである。
備考
題を「山中俗人に答(こた)う」とするものもある。出典は「李太白文集」で「唐詩選」にはない。
参考
陶淵明の「桃花源の記」の一節
世に「桃源郷」と言われる理想郷を空想した名文がある。李白のこの詩、特に転句はこれを踏まえているというのは定説となっている。要点のみ紹介する。
「晋の時代、ある漁師が桃の花咲く川をさかのぼっていくと、山に穴が開いていた。不思議に思って入ってゆくと、そこは土地も広く、家々が整然と並び、見事な田畑や池があり、道が縦横に伸びている。鶏や犬が啼き、その中で人々は農作業に励み、生活を楽しんでいる。村人は漁師を家に招き歓迎した。彼らは秦の世の戦乱をのがれて絶境に来て以来、他の地へ出ることなく長くこの地に住んでおり他所(よそ)さまとは関(かかわ)りあいがなくなってしまった。何も知ることができなかった。今は一体どういう時世なのですか?。(以下略)」
詩の形
二四不同・二六同、下三連は不可、弧平・弧仄を忌むの原則が守られていないので七言古詩の形であって、上平声十五刪(さん)韻の山、閑、間の字が使われている。あえてこの詩に限っては型破りの味わいをねらう意味があるのだろう。第二句の「而」の字は普通、詩には用いないものであるが、「論語」の中ではよく見るので、作者は面白いと思ったか字数を整えるのに用いたかは分からない。論語では「て」又は「にして」とも読まれているので「笑って」の「て」と読むと理解すればよいだろう。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
李 白 701~762
盛唐時代の詩人
四川省の青蓮(せいれん)郷の人といわれるが出生には謎が多い。若いころ任侠の徒と交わったり、隠者のように山に籠ったりの暮らしを送っていた。25歳ごろ故国を離れ漂泊しながら42歳で長安に赴いた。天才的詩才が玄宗皇帝にも知られ、2年間は帝の側近にあったが、豪放な性格から追放され、再び漂泊した。安禄山の乱後では反朝廷側についたため囚われ流罪(るざい)となったがのち赦(ゆる)され、長江を下る旅の途上で亡くなったといわれている。あまりの自由奔放・変幻自在の性格や詩風のためか、世の人は「詩仙」と称えている。酒と月を愛した。享年62。
