漢詩紹介
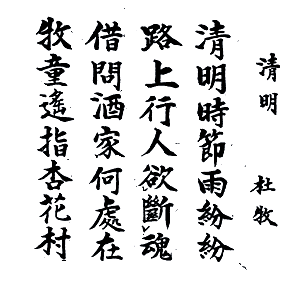
吟者:稲田菖胤
2010年8月掲載
読み方
- 清 明 <杜 牧>
- 清明の時節 雨紛紛
- 路上の行人 魂を断たんと欲す
- 借問す酒家は 何れの処にか在る
- 牧童遥かに指さす 杏花の村
- せいめい <とぼく>
- せいめいのじせつ あめふんぷん
- ろじょうのこうじん こんをたたんとほっす
- しゃもんすしゅかは いずれのところにかある
- ぼくどうはるかにゆびさす きょうかのむら
詩の意味
清明の季節であるのに、あいにく雨がしとしとと小止みなく降りつづき、道ゆく旅人(私)も愁いに沈み、魂も消えいりそうである。
(酒でも飲んでその心を晴らそうと思い)通りあわせた牛飼いの少年に、酒屋はどのあたりにあるかと尋ねたら、はるかかなたの杏(あんず)の咲く村を指さして教えるのであった。
語句の意味
-
- 清 明
- 清明節の日 二十四節気のひとつで春分の日から数えて15日目 新暦では4月5日ごろ
-
- 紛 紛
- 雨などがさかんに降るさま
-
- 行 人
- 旅人 ここでは作者
-
- 断 魂
- 心が滅入って悲しくなる
-
- 借 問
- 試みに尋ねる
-
- 杏
- 梅によく似た果樹 種は薬用
鑑賞
単なる叙景詩で終わらせたくない名詩
この詩が詠まれたのは江南の池州(ちしゅう)の刺史(しし)を勤めていた44歳のころで、比較的役人としての充実感を得、弟一家の面倒も十分看ることができて幸せな時期とある。この詩は意外に難解である。まず清明のころは好季節で、花も一斉に咲き、風も穏やかで晴天が多いのが普通なのに、この日は思いがけない悪天候であるから作者は気が滅入って憂うつなのである。次に、牧童に酒屋を聞いたらあっちだよと杏の咲く村を指さして教えてくれたと、詩はここで終わっているが、その意図は何であろう。杏の花はあわい紅か白色系である。その林は満開で、美しさは梅林にも匹敵する見事さだという評もある。春雨の中にけむる花霞(はながすみ)に、作者は思いがけない美しさを発見し、忽ち感動したのであろう。
この詩が叙景詩で終わるなら解説もここまでだが、そうではない。一気に心の憂(う)さが晴れていく作者がいる。憂さ晴らしに酒でも飲もうといった安っぽい動機が、純朴な少年のふるまいと花霞によって払いのけられたのであろう。「雨のち晴」の清々(すがすが)しい心の移ろいが読み取れる。
備考
訳詩 星野哲史
しっぽり濡るる春雨に
旅の思いのやるせなさ
せめて一献憂さ晴らし
酒を求めて道問えば
わらべは指さす 杏花の村
参考
杏林とは医者の美称
杏の種は薬用になる。三国時代、呉の董奉(とうほう)という医者は貧しい者から治療代を取らないで、重症者には5本、軽症者には1本の杏の木を植えさせた。数年で杏の林ができて、多くの患者がこの恩恵を受けたという故事がある。そこから杏林は医者の美称となった。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声十二文(ぶん)韻の紛と十三元(げん)韻の魂、村の字が通韻して使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
杜 牧 803~852
晩唐の政治家・詩人
字は牧之、号は樊川(はんせん)。京兆(けいちょう=今の西安)の名門の出身。23歳の時「阿房宮(あぼうきゅう)の賦(ふ)」を作り、その天才ぶりが世に知れ渡った。26歳で進士となり、江蘇省の楊州に赴任した時代には名作を多く残している。杜牧は美男子で歌舞を好み、青楼に浮名(うきな)を流したこともあるが、その人柄は剛直で、大胆に天下国家を論じたりもした。33歳の時、中央政府の役人になるが、弟が眼病を患っていたので、弟思いの杜牧は自ら報酬の高い地方官を願い出て面倒を見た話は、また別の一面を語っている。中書舎人(ちゅうしょしゃじん)となって没す。享年50。「樊川文集」20巻、「樊川詩集」7巻がある。
