漢詩紹介
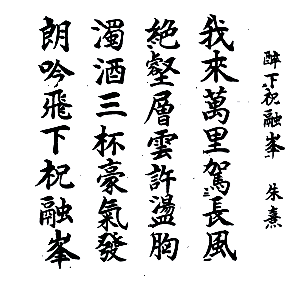
吟者:山口華雋
2010年8月掲載
読み方
- 酔うて祝融峰を下る <朱 熹>
- 我来って万里 長風に駕す
- 絶壑の層雲 許胸を盪かす
- 濁酒三杯 豪気発し
- 朗吟飛び下る 祝融峰
- よオてしゅくゆうほうをくだる <しゅき>
- われきたってばんり ちょうふうにがす
- ぜつがくのそううん かくむねをうごかす
- だくしゅさんばい ごうきはっし
- ろうぎんとびくだる しゅくゆうほう
詩の意味
万里の彼方から吹いてくる風に乗って、ここ祝融峰の頂きに登って来た。四方を見下ろせば、底知れぬ深い谷間より湧き上がる雲は幾重にも重なり、わが心を揺り動かしてやまない。
かくして、濁り酒を幾杯か飲むと、勇気が湧いてきた。得意の詩を朗吟しつつ、この名高い霊山祝融峰を飛ぶがごとく一気に下ったが、実に爽快なことだ。
語句の意味
-
- 祝融峰
- 湖南省中部に在り 衡山(こうざん)連峰の中の一つ この連峰は南の回雁(かいがん)峰(衡陽=こうよう=市内)から北の岳麓(がくろく)山(長沙市の西郊)に至る約400キロメートルの山なみで大小72の峰からなり中でも祝融(1290メートル)、天柱、芙蓉、紫蓋(しがい)の峰が有名
-
- 絶 壑
- 深い谷
-
- 層 雲
- 重なっている雲
-
- 許
- かくのごとく
鑑賞
書斎に向かう学者と思えぬ青年朱熹ここに在り
祝融峰は1290メートルとある。比叡山が848メートル、高野山が985メートルだからかなり高い。冬はとても登れまいから、この詩は夏と思われる。年齢も不明だが山頂で酒を飲んで飛び下るという技ができるのは30代まで。青年時代の作であろう。
朱熹は学者の印象が強い。地方役人として各地を転々としながら、遺(のこ)した著書はいずれも歴史に残る大作ばかりである。「近思録」「四書集注(しっちゅう)」の四冊、「楚辞集注」など。ひたすら机に向き合っている姿が似合うだけに、この詩のように屋外に飛び回る作者がなかなか想像しにくい。しかし、温厚篤実(とくじつ)だと言われる朱熹の意外な半面を知って実に新鮮である。男性的な、動きのある描写範囲の広い作品となっている。祝融峰に登ること自体が奔放な行為ともいえるが、その上、「万里」「長風」「絶壑」などの遠景描写でつなぎ、「豪気」の語を挟んで最後は「飛び下る」ときて、雄大かつ豪快な詩語で終わる。登山家朱熹の貴重な詩である。登山をした折には山頂で吟じるのにうってつけであろう。
参考
通韻(つういん)(初学者は行わないように)
通韻とは、本来使用される本韻字に対して、ひびきのよく似た他韻字を用いて、同一韻に通じさせることをいう。古体詩(古詩)を一韻到底で作る場合、一韻に拘らず通用させる。但し、通用し得る韻種は決まりが有って、例えば東、冬、江の各韻は通用出来るなどの如く範囲に限定があり、韻書、韻目表に依る。
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、上平声一東(とう)韻の風と二冬(とう)韻の胸、峯の字が通韻して使われている
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
朱熹 1130~1200
南宋の哲学者・役人・詩人
朱子学の創始者。字は仲晦(ちゅうかい)または元晦、名は熹、号は晦庵(かいあん)、晦翁、紫陽(しよう)などあり、朱子はその尊号。福建省建州に生まれる。詔興18年(18歳)に進士に及第した秀才。李侗(りとう=李延平=りえんぺい)に師事する。宋代に始まった新しい儒学を首尾一貫した体系にまとめ、朱子学を完成した人。朱子学は徳川幕府の官学として権威があり、近年まで我が国の思想の背景をなした。著書「論語集注(しっちゅう)」「孟子集注」などは今でも中国思想研究者には必読の書である。慶元6年没す。享年71。
