漢詩紹介
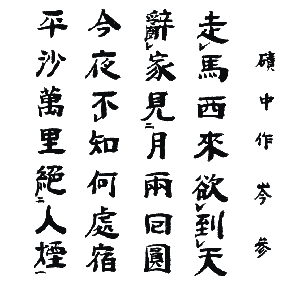
吟者:埜辺旭洲
2010年11月掲載
読み方
- 磧中の作 <岑 参>
- 馬を走らせて 西来 天に到らんと欲す
- 家を辞してより 月の両回 円かなるを見る
- 今夜は知らず 何れの処にか宿せん
- 平沙 万里 人煙絶ゆ
- せきちゅうのさく <しんしん>
- うまをはしらせて せいらい てんにいたらんとほっす
- いえをじしてより つきのりょうかい まどかなるをみる
- こんやはしらず いずれのところにかしゅくせん
- へいさ ばんり じんえんたゆ
詩の意味
馬を走らせて西へ行けば、地平線は果てしなく天まで続いていて尽きることがない。もう家を出てから2回も満月の夜を迎えたのだ。
今夜はどこに野宿するのだろうか、何のあてもない。見渡す限り月下に広がる沙漠は果てしなく続いて、人家の煙さえ見えないのだ。
語句の意味
-
- 磧 中
- 砂漠の中
-
- 西 来
- 西に向かっていく「来」は語勢を強める助字
-
- 月両回円
- 満月が2回 2か月が過ぎること
-
- 平沙万里
- 平らかな砂漠が遥か遠くまで続いている
-
- 人 煙
- 人家の生活する煙
鑑賞
孤独で心細い旅人の心境を歌った傑作
この詩の制作年代ははっきりしないが、作者は天宝8年(749)に節度使の下級役人として安西に赴任している。3年後には北庭(新彊省チムサル県)に行き、翌年には同省の輪台に生活するなど辺塞生活を経験しているから、このころの作と思われる。この詩は辺塞詩のうちでも名作中の名作と言われているが、日本人には想像もつかない描写の連続で圧倒される。地平線が天に届くほど行く道は永遠に続くとか、馬とともに2か月も旅を続ける生活。食料や水はどうしていたのかと素朴な疑問がわくが、答えは見当もつかない。そして砂の上の野宿。もし冬なら零下何十度にもなる極寒の地である。さらに行けども行けども人家は見えない。その心細さは地獄に誘導されるようではなかったか。それでもなお役目を背負って行かなければならなかった役人の悲壮さは想像を絶する。
備考
「絶人煙」は「人煙絶ゆ」か「人煙を絶つ」か
結句の「絶人煙」は中国語の語順からすれば動詞+目的語だから「人煙を絶つ」と読むのが正式だ。もし「人煙絶ゆ」と読むなら「人煙絶」とならなければならない。本会では人家の煙は全く見えないという意味を優先させて「人煙絶ゆ」と訓読している。簡野道明氏の「唐詩選詳解」では「人煙を絶つ」と読んでいる。
参考
節度使とは
官名。唐、宋時代に軍政と行政をつかさどった地方長官。今流にいえば外国大使ほどの地位と権力を備える。唐の玄宗皇帝時代には10の節度使を置いて地方の治安を守らせた。反乱をおこした有名な安禄山は平廬、范陽、河東の3節度使を兼ねていて強力な権限を持っていた。元の時代に廃止された。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であるが、起承句は仄起式、転結句は平起式の声調になっているので拗体である。下平声一先韻の天、円、煙の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
岑参 715~770
盛唐の役人・詩人
南陽(河南省)の人とも。名門の出身で兄弟そろって秀才の誉れ高く、天宝3年(744)2番の成績で進士の試験に合格した。官を重ねて左補闕(さほけつ)・起居郎(ききょろう)となり、749年には節度使属官として十余年にわたり辺塞の地に参軍した経験を持つ。嘉州(四川省)の刺史に進み、のち職を辞して杜陵山中に隠棲して、蜀で客死す。辺塞詩人として知られている。「岑嘉州集」(しんかしゅうしゅう)7~8巻がある。享年55。
