漢詩紹介
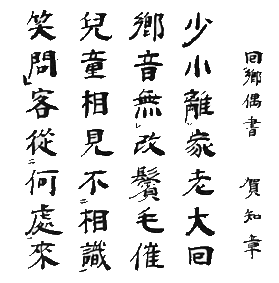
読み方
- 鄕に回りて偶書す<賀知章>
- 少小にして家を離れ 老大にして囘る
- 鄕音改まる無く 鬢毛催す
- 兒童相見て 相識らず
- 笑って問う客は 何處從り來るかと
- きょうにかえりてたまたましょす<がちしょう>
- しょうしょうにしていえをはなれ ろうだいにしてかえる
- きょうおんあらたまるなく びんもうもよおす
- じどうあいみて あいしらず
- わらってとうかくは いずこよりきたるかと
字解
-
- 少 小
- 若いころ
-
- 老 大
- 年とってから
-
- 鄕 音
- いなかのなまり 生まれ故郷のなまり
-
- 鬢毛催
- 髪の毛が白く老いさらぼうこと
-
- 兒 童
- 近所の子どもでなく一族内の子どもと解す可きである
意解
若い時に故郷を出て年老いて今帰って来た。何年たっても故郷のなまりはなおらないが、頭の髪の毛は白くなってしまった。子供達は自分がこの土地の者だということを知らず、自分もどこの家の子かも分からない。笑いながら「おじさんはどこから来たのですか」と問いかけるのであった。
備考
承句の催が摧となっているものもある。この詩の構造は仄起こり七言絶句の形であって、上平声十灰(かい)韻の囘、催、來の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
賀知章 659-744
盛唐の詩人、字は季真(きしん)、越州永興(えっしゅうえいこう 淅江省蕭山県(せっこうしょうしょうざんけん))の人、則天武后(そくてんぶこう)の証聖(しょうせい)元年(695)の進士、玄宗の開元十三年(725)礼部(れいぶ)侍郎にいたる。杜甫の飲中八仙の一人。酒を飲む。晩年故郷に帰って間もなく死す。年86。
