漢詩紹介
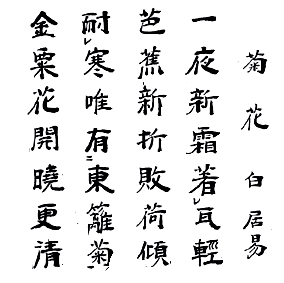
読み方
- 菊 花 <白居易>
- 一夜新霜 瓦に著いて軽し
- 芭蕉は新たに折れて 敗荷は傾く
- 寒に耐うるは唯 東籬の菊のみ有って
- 金粟の花は開いて 暁更に清し
- きっか <はくきょい>
- いちやしんそう かわらについてかろし
- ばしょうはあらたにおれて はいかはかたむく
- かんにたうるはただ とうりのきくのみあって
- きんぞくのはなはひらいて あかつきさらにきよし
詩の意味
一夜明けると、今年初めての霜がうっすらと降りて、瓦を白くしている。この寒さに、芭蕉は新たに折れ、破れた蓮の葉も傾いてしまった。
そうした寒さに耐え、毅然(きぜん)としているのは、ただ東籬の菊だけで、美しく咲いたその菊の花は、暁の風景を一層清らかにしている。
語句の意味
-
- 新 霜
- 初霜
-
- 芭 蕉
- バショウ科の大形の多年生草本 草本は水分の多い植物の総称
-
- 敗 荷
- 「荷(か)」は蓮 枯れて破れた蓮の葉
-
- 東 籬
- 東の籬(まがき) 「籬」は竹、柴などを粗く編んで作った垣
-
- 金 粟
- ここでは菊
鑑賞
菊の花が最も愛されるのは重陽の節句
菊の高貴さが作者宅の庭の夜明けに清々しさを漂わせる光景を詠じている。作者が長年暮らした長安の緯度は日本の大阪あたりに相当するから、季節感としては、あまり差がないものと考えてよい。日本でも初霜のある10月下旬が、この花の見頃である。
ところで中国では重陽の節句(9月9日)の宴で、この花びらを酒に浮かべて楽しむ風習があるから、とりわけ菊が尊ばれたのはその日までであったようである。次の詩と比較するとそれがわかる。
十日の菊 (晩唐)鄭 谷
節去蜂愁蝶不知 節去り蜂愁えて蝶知らず
暁庭還繞折残枝 暁庭に還た折り残せる枝を繞る
自縁今日人心別 自ら今日の人心の別なるに縁る
未必秋香一夜衰 未だ必ずしも秋香は一夜にして衰えじ
(重陽の)節句が過ぎてしまったのを蜂は愁えているが、蝶は気づかないで、明け方の庭に、昨日折
りしだかれた菊の枝をなおも飛び巡っている。(菊の色香が昨日と変わって見えるのは)今日の人の
心が変わってしまったからなのであって、花自身の秋の香が一夜にして 衰えてしまったわけではありません。
つまり人心は蜂や蝶にも劣っていると風刺した詩。引退するとやがて人は訪ねてこなくなるという、人情の薄さを嘆く歌ともとれる。日本にも「六日の菖蒲」という言葉があるが同意である。
備考
「東籬の菊」はいうまでもなく 陶淵明の五言古詩「飲酒」の中にある、世俗を去った淵明が自庭の菊を眺めて心の満足を歌った部分からの引用である。その3句・4句は「菊を採る東籬の下 悠然として南山を見る」とある。国語辞典によると「菊を採る東籬の下」の1句は(菊を酒に浮かべるために摘むという意から)俗世間を離れた境地を例える慣用句とある。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声八庚(こう)韻の軽、傾、清の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
白居易 772~846
中唐の政治家・詩人
名は居易、字は楽天、号は香山居士(こうざんこじ)。陝西省渭南(せんせいしょう いなん)の人(太原の人ともいう)。家は代々官吏であった。早くから詩を作り、16歳で「春草の詩」、17歳で「王昭君」の作がある。貞元16年(800)の進士。同期の進士、元稹(げんしん)と深い親交があった。江西省九江の司馬に左遷されたこともあるが、ほぼ中央の官にあった。「長恨歌(ちょうごんか)」「琵琶行」の大作を遺す。「白氏長慶集(はくしちょうけいしゅう)」「白氏文集(もんじゅう)」等が我が国にも伝わり、平安文学に感化影響を与えた。晩年は刑部尚書(けいぶしょうしょ=法務大臣の格)にて没す。享年75。
