漢詩紹介
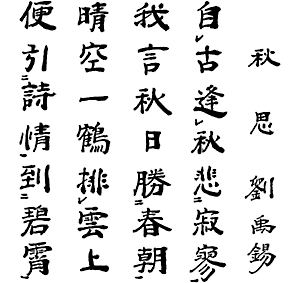
CD④収録 吟者:川村朋映
2016年4月掲載
読み方
- 秋 思 <劉禹錫>
- 古自り秋に逢うて 寂寥を悲しむ
- 我は言う 秋日 春朝に勝ると
- 晴空一鶴 雲を排して上る
- 便ち 詩情を引いて 碧霄に到る
- しゅうし <りゅううしゃく>
- いにしえよりあきにおうて せきりょうをかなしむ
- われはいう しゅうじつ しゅんちょうにまさると
- せいくういっかく くもをはいしてのぼる
- すなわち しじょうをひいて へきしょうにいたる
詩の意味
昔から人は秋になると、もの寂しく悲しい思いをするが、自分は秋の日なかの方が春の朝にも勝っていると言いたい。
晴れわたった秋空高く一羽の鶴が、雲を押し分けるようにして舞い上がって行く。それは人の歌心を誘うようで、共に大空の上まで昇りつめるようである。
語句の意味
-
- 寂 寥
- 物静かでさみしい
-
- 秋 日
- ここでは春朝に対して秋の日差しの輝く時
-
- 便
- それは
-
- 碧 霄
- 碧空 あおぞら 「霄」は天空
鑑賞
悲運の作者に差し込んだ希望の光
確かに多くの詩人は、秋といえば物静かでさびしい情を詠んでいる。承句の「春朝」には孟浩然の「春暁」が想定されるが、「秋日」を際立たせる伏線である。後半2句は無条件に明るい。1羽の鶴が真っ青な天空に舞い上がり、作者もその光景に誘われて詩情が湧くという明朗さは、なかなか他の詩にみられない。もっとも鶴が群れを離れて1羽のみ上空に舞い上がるということは現実にはありえないから、作者の空想であろうと思えるが、その詮索は今置いておく。もしかすると長い地方役人から解放されて都に帰還を許された折の詩かもしれない。希望が満ち溢れている。
しかし劉禹錫のもっとも有名な詩は「秋風の引(いん)」で、やはり秋の感慨を詠じている。同じ作者の趣向が違っていてなんら不思議はないが、読み比べてみると一層鑑賞が深まる。
秋風の引 劉禹錫
何処秋風至 何れの処よりか秋風至り
蕭蕭送雁群 蕭蕭として雁群を送る
朝来入庭樹 朝来庭樹に入って
孤客最先聞 孤客最も先に聞く
(どこから吹いてくるのか、秋風が訪れて、雁の群れを寂しく南の方へ吹き送っている。今朝方から庭の植え込みに吹き込んで、梢をさらさら鳴らしているが、真っ先にそれを聞きつけて、ひしひしと秋をかみしめている者は、孤独な旅人であるこの自分である)
この詩は本会では採択されていないが、彼の代表作である。「秋思」に比べれば明と暗の違いがあり、かなり湿っぽい。地方に左遷された期間が10年以上になることもあったので、故郷への思いは募ったであろう。結句がことに有名である。誰よりも秋風の訪れを真っ先に知ったということは、誰よりも先に秋の寂寥感を感じ、望郷の念に沈んでいるということになる。秀才の作者にも訪れた悲運の日々を思うとき、この詩は普遍性と説得力がある。
2題の詩を通して、波乱の生涯を送った人間劉禹錫が理解できるのではなかろうか。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声二蕭(しょう)韻の寥、朝、霄の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
劉 禹錫 772~842
中唐の政治家・詩人
河北省定県の人。または彭城(ほうじょう=江蘇省徐州市)の人。字は夢得(ぼうとく)、禹錫は号。貞元9 年(793)柳宗元と同時に進士に及第した。中央役人も勤めるが、進歩的性格のためか、作詩の趣旨が不快を与えたのか、たびたび長期にわたり左遷されている。最後は検校礼部尚書(=けんこうれいぶしょうしょ 礼楽、祭祀、教育などを司る役の名誉長官)で終わる。生年を同じくする白居易とも親交があり、ともに詩に巧みであったので「劉白」と称された。「劉賓客文集」などがある。享年71。
