漢詩紹介
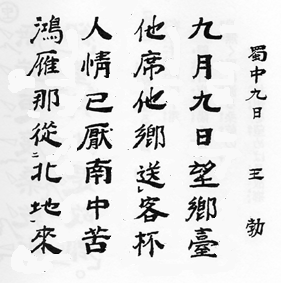
読み方
- 蜀中九日 <王 勃>
- 九月九日 望郷台
- 他席他郷 客を送るの杯
- 人情已に厭う 南中の苦
- 鴻雁那ぞ 北地従り来る
- しょくちゅうきゅうじつ <おうぼつ>
- くがつここのか ぼうきょうだい
- たせきたきょう かくをおくるのはい
- にんじょうすでにいとう なんちゅうのく
- こうがんなんぞ ほくちよりきたる
詩の意味
9月9日重陽の節句に、故郷を望んで望郷台に登った。そこはよその国のよその宴席であるが、旅立つ友を送る杯を酌み交わしていた。
私の気持ちは、もう南の地での暮らしに飽きて嫌気がさしているのに、あの雁の群れはなぜ北を捨てて南に飛んで来るのだろう。
語句の意味
-
- 蜀 中
- 四川省蜀の国 ここでは成都
-
- 客
- 旅人
-
- 南中苦
- 蜀の国の生活のわびしさ
-
- 鴻 雁
- おおきな鴻と小さな雁 秋になると南方の地へ渡ってくる
鑑賞
南にやってきた雁の群れには何の罪もない
長安の役人であったころ諸王の間で闘鶏が流行していたのに対し、檄文を書いたため高宗の怒りに触れ、免職になって四川省に流謫された。その地でたまたま9月9日の節句の宴に出くわし、望郷台に登って思いを述べた詩である。
初唐は近体詩がまだ確立していない頃で、この詩も平仄の決まりが守られていない。ただ「九月九日」とか「他席他郷」などたたみかけるような語調は、盛唐になるとあまり見かけられないが、この場合は語意が強調されている分、わかり易くなっている点は評価される。
作者の境遇を確認しておきたい。四川省成都といえば、今でこそ大都会であるが、都から遠く、しばしば左遷の地であって、僻地である。納得いかない流謫で面白くない毎日であった。「北(長安および生まれ故郷)へ帰りたい」という思いが募ってきたのである。たまたま出くわした宴席では送別会が開かれている。その人はおそらく北に向かって出発するのであろう。羨ましさがのぞいている。そんな気持ちも知らないで、雁の群れが喜びの声を立てながら新天地を目指して北から飛んで来た。北へ帰りたい作者の心に逆らって自分を嘲っているように感じたのではないか。満たされぬ望郷の思いが無言のうちに伝わってくる。そして一度も北に帰ることなく28歳の若さで南の海に消えたことを思えば、そのせつなさが増幅される。
参考
①「望郷台」はどこにあったのか確証がない
一つは蜀の東部にある玄武山に設けられていたという説(全唐詩)。二つめは成都の北にあり、隋の蜀 王秀が築いたというもの(旧説・杜詩注)
②「重陽の節句」を詠った詩は多い
有名な詩では「九月九日山中の兄弟を憶う」(王維)。日本では「秋思詩」「九月十日」(菅原道真)など。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であるが、平仄が整わず(起句の二四不同・二六同)、拗体であって、上平声十灰(かい)韻の台、杯、来の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
王 勃 649~678
初唐の詩人・役人
字は子安、父は王福、祖父は王通といい学者の家の出である。山西省河津県絳州龍門(かしんけんこうしゅうりゅうもん)の人。20歳前に高宗(こうそう)の試問に応じ朝散郎の官を授けられたという秀才で、のち沛王府の修撰(史書の監修役)という職についた。のち高宗の怒りを買い、蜀の国に流謫(るたく)される。父の王福も同時に交趾令(こうちれい=今の北ベトナム)に左遷された。王勃は大赦で出獄し、父を訪ねて南方に出、南海の海に落ちて死す。享年28。
