漢詩紹介
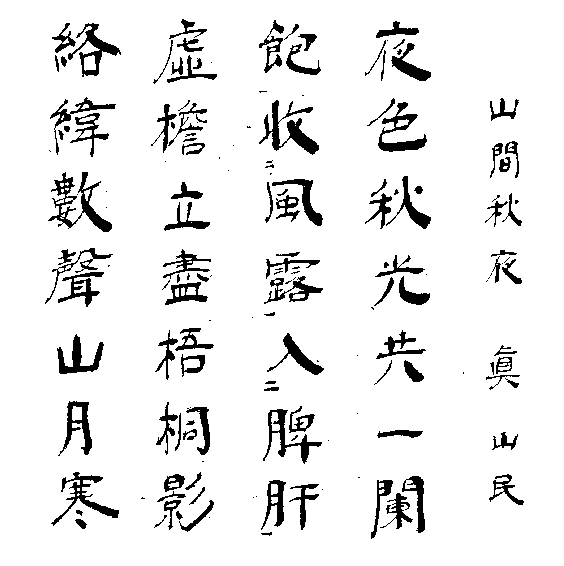
吟者:古賀千翔
2017年8月掲載
読み方
- 山間の秋夜 <真山民>
- 夜色秋光 共に一闌
- 飽くまで風露を収めて 脾肝に入る
- 虚檐立ち尽くす 梧桐の影
- 絡緯数声 山月寒し
- さんかんのしゅうや <しんさんみん>
- やしょくしゅうこう ともにいちらん
- あくまでふうろをおさめて ひかんにいる
- きょえんたちつくす ごどうのかげ
- らくいすうせい さんげつさむし
詩の意味
更けゆく秋の夜色と月光が一つの欄干に満ち、心ゆくまで夜風と露で感じる夜気を身中、心ゆくまで吸い込む。
誰もいない軒端(のきば)で、青桐の影の辺りにしばらく立っていると、どこからともなく、たくさんのこおろぎの鳴く声が聞こえて、山の端(は)にかかる月に、ひとしお冷ややかな、もの寂しさを覚えるのであった。
語句の意味
-
- 一 闌
- 「闌」は欄に同じ 一つの欄干
-
- 脾 肝
- 脾臓と肝臓 腹の中
-
- 虚 檐
- 誰もいない軒先
-
- 梧 桐
- 青桐
-
- 絡 緯
- こおろぎ くつわむしなど
鑑賞
南宋末の役人が晩年に求めたもの
詩題の「山間の秋夜」から時と場所はすぐわかるのに、詩中に季節を表す詩語が多いのが、この詩の特色といえよう。すなわち「秋光」「風露」「梧桐」「絡緯」さらに「山月」と続く。日本でも「つゆ」「こおろぎ」は秋の季語である。この詩も初秋の頃とみたい。具象語が多いので実景が描きやすい。
さてこの詩の主題は何であろう。秋を迎えて老境を嘆くとか、故郷が偲ばれるとか、かつての栄華が浮かぶというような主題は、この詩には見つからない。真山民の晩年の厭世思考に照らし合わせると、今までの政治上での名誉や活躍にも一切未練を示さず、ひたすら世俗との縁を切り、ただ秋の夜の風情に浸りつつ、同化していこうとしている姿がうかがえる。これがこの詩の主題ではないか。それは二句目の、秋気を全身で受け入れながら心の安定を得るという7文字がそれを裏づけている。
参考
①遺民(滅んだ国の人で新しい朝廷には仕えない人)について
関西吟詩に採用されている南宋末の遺民は「別妻子良友」の謝枋得、「過零丁洋」の文天祥がその代表である。いずれも有能な政治家であって忠義心に富む。たとえ極刑になろうとも元には仕えないという魂には畏怖さえ感じる。真山民の場合は直接元に抵抗したという記録はなく、むしろ隠棲の晩年であったとあるが、遺民には違いない。
②滅びに至る南宋
宋が建国されたのは960年である。当時から絶大な強国ではなく、すでに北方民族の契丹(遼)に脅かされていた。その70年後に契丹にとって代わった金王国によって、宋は中原を追われて南の臨安(杭州)を都として南宋を立てた。しかし金国の圧力は根強く、たとえば南宋は金国に対し臣下の礼を採ること、また毎年銀25万両と絹25万匹を贈与することを約束させられて、何とか国を維持してきた。その150年後に、ついに宋は金国を滅ぼした北方民族モンゴルの雄者フビライによって滅亡する。遺民と呼ばれる人は、蛮族と卑下してきた北方異民族の臣下になることは、あくまで漢民族の誇りが許さなかったのであろう。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声十四寒(かん)韻の闌、肝、寒の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
真山民 生年不詳~1274頃か?
南宋末の進士で哲学者
名は桂芳(けいほう)というが、出身地など詳しいことはわからない。宋末の遺民で世を逃れ、人に知られることを求めず、自分で山民と呼ぶ。欧陽修、朱熹、蘇東坡と共に宋代の代表的詩人といわれ、特に叙景詩に優れている。
