漢詩紹介
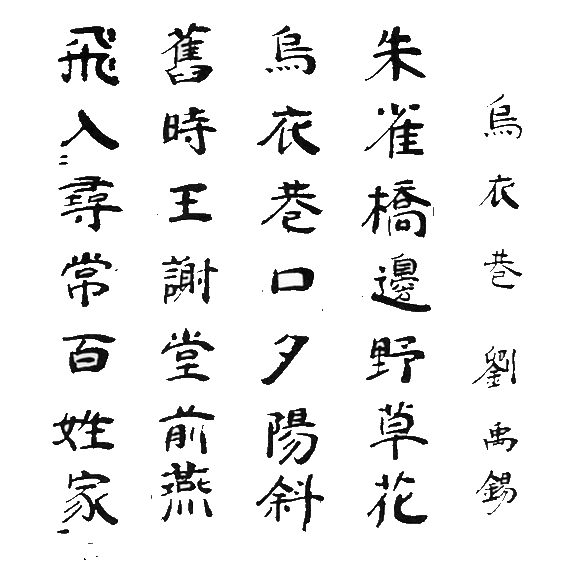
読み方
- 烏衣巷 <劉禹錫>
- 朱雀橋辺 野草の花
- 烏衣巷口 夕陽斜めなり
- 旧時王謝 堂前の燕
- 飛んで尋常 百姓の家に入る
- ういこう <りゅううしゃく>
- すじゃくきょうへん やそうのはな
- ういこうこう せきようななめなり
- きゅうじおうしゃ どうぜんのつばめ
- とんでじんじょう ひゃくせいのいえにいる
詩の意味
六朝時代に栄えた朱雀橋の辺りは、今は荒れ果て、野の草花が咲き、烏衣巷と呼ばれた町の入り口には夕日が斜めにさしこんでいる。
昔、王氏や謝氏の邸宅に巣を作っていた燕が、今は庶民の家の軒先に飛び入って巣を作っている。
語句の意味
-
- 烏衣巷
- 金陵(南京)の町の名 「巷」は小さな町
-
- 朱雀橋
- 朱雀門(都の南門)の外の秦淮にかかっていた橋
-
- 王 謝
- 南朝最大の貴族 王氏と謝氏
-
- 堂 前
- 「堂」は邸宅の表座敷 邸宅のあたり
-
- 百 姓
- 人民 庶民
鑑賞
栄枯盛衰の変遷を詠う
作者は53歳の時から約2年間、和州(安徽省和県)刺史として在任中に、「金陵五題」と題する五首連作の懐古詩を作った。この詩はその第二首目である。
烏衣巷は六朝時代に栄えた金陵に在った町の名で、ここには南朝切っての名門貴族といわれる王氏や謝氏の大貴族が豪邸を構えて住み、その子弟が皆烏衣(黒い衣服)を着ていたので、この名がある。その約500年後に作者はその入り口に立って時代を懐古している。昔の金陵は華やいだ町と考えればよい。「朱雀橋」「烏衣巷」「王謝」の語がそれを物語る。ところが「野草花」「夕陽斜」「百姓」という語句は、にぎわいを失ったさびれた町の様子をうかがわせる。さらにかつては雅(みやび)やかな貴族の暮らしを空想させる「雅」の反意語の「野」を配置して、栄枯盛衰の変遷を対照的に象徴させているのは、この詩の味わいどころである。さらに燕を「王謝」と「百姓」、言いかえれば過去と現在を繋ぐ素材として登場させている発想の良さも、もう一つの味わいどころであろう。
一方燕は、人の世の興亡とか富貴の区別なく、生き生きと適所に巣を作る。もしかすると、燕こそあるべき生きざまを知っていて、人間どもの、富貴を願う、はかなく愚かしい生き方に、無言のうちに警鐘を鳴らしている詩ではないか。作者は秀才で将来の宰相の人望もあったといわれるが、一族の失脚や周囲の誤解で左遷を繰り返された人生から、にじみでた描写である。
参考
「金陵五題」の第一首「石頭城」
- 山囲故国周遭在
- 山故国を囲みて 周遭(しゅうそう)として在り
- 潮打空城寂莫回
- 潮は空城を打ちて 寂莫として回る
- 淮水東辺旧時月
- 淮水(わいすい)東辺 旧時の月
- 夜深還過女牆来
- 夜深くして還た 女牆(じょしょう)を過(よぎ)って来たる
- (詩意)
- 山は古い都をぐるりと取り囲み
長江の潮はうつろな城に打ち寄せて 寂しく波立ち回り流れている
淮河の東からは昔と変わらず月が昇り
夜更けともなれば城の女牆を越えてまたやって来るのである
(女牆=城の上の低い垣)
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声六麻(ま)韻の花、斜、家の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
劉禹錫 772~842
中唐の政治家・詩人
河北省定県の人。または彭城(ほうじょう=江蘇省徐州市)の人。字は夢得(ぼうとく)、禹錫は号。貞元9年(793)柳宗元と同時に進士に及第した。中央役人も勤めるが、進歩的性格のためか、作詩の趣旨が不快を与えたのか、たびたび長期にわたり左遷されている。最後は検校礼部尚書(礼楽、祭祀、教育などを司る役の名誉長官)で終わる。生年を同じくする白居易とも親交があり、ともに詩が巧みであったので「劉白」と称された。「劉賓客文集」などがある。享年71。
