漢詩紹介
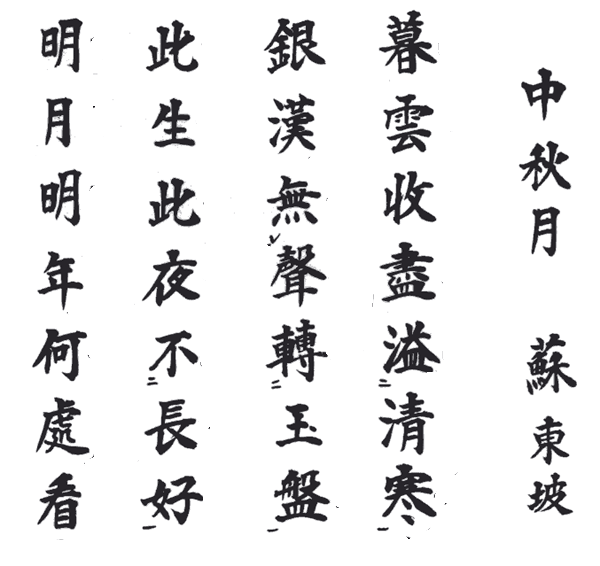
読み方
- 中秋の月 <蘇 東坡>
- 暮雲収まり尽くして 清寒溢る
- 銀漢声無く 玉盤を転ず
- 此の生此の夜 長しえに好からず
- 明月明年 何れの処にか看ん
- ちゅうしゅうのつき <そ とうば>
- ぼうんおさまりつくして せいかんあふる
- ぎんかんこえなく ぎょくばんをてんず
- このせいこのよ とこしえによからず
- めいげつみょうねん いずれのところにかみん
詩の意味
夕暮れの雲は跡かたもなく、清々しい冷気が夜空に満ちている。天の川は音もなく玉の皿のような月を天上にめぐらせている。
限りあるわが生涯、いつまでもこのような素晴らし明月の夜に会えるとは限らない。この明月のすばらしさを明年はどこで観ることであろうか。
語句の意味
-
- 収 尽
- 収まりなくなる
-
- 清 寒
- 清々し冷気
-
- 銀 漢
- 天の川
-
- 転
- めぐる まわる
-
- 玉 盤
- 月の異名
-
- 不長好
- いつも良いとは限らない
鑑賞
定めがたいものそれが人生
作者41歳の時、弟の轍(てつ)とともに暮らした彭城(=ほうじょう 江蘇省銅山県)での作である。1点の雲もなく、清々しい秋の気配に、天の川がかかり明月がゆっくりと動くという中秋の空は美しいうえに神秘的であり、宇宙の芸術ともいえる。こんな夜はめったに出会えるものではないと転句で実感を述べている。それは人の世が定めがたいことを知っているからである。ここにこの詩の主題がある。事実、翌年には作者は江蘇省の徐州の地に移り、病床にあって中秋を迎えているし、弟は南京に行ってしまった。この作者の詩は「春夜」の「春宵一刻値千金」があまりにも有名だけれどこの秋の詩も奥が深く捨てがたい。
備考
部分否定の読み方
転句の「不長好」は「長へには好からず」と読んで「いつまでもよいとは限らない」と部分否定であることを強調する読み方もあるが本会では採らない。
参考
陽関詞について
この詩は陽関詞と呼ばれる3首のうちの1首である。別名渭城曲と言う。つまり王維の「元二の安西に使いするを送る」と同じ曲調で歌われたということである。どういう曲かはここに示せないが、2つの詩の平仄を見れば28文字のうち1字だけが違っているがほぼ同じ音調とみてよい。当時渭城曲として大いに歌われたことが想像できる。(「漢詩体系・蘇軾」)
詩の形
平起こり七言絶句の形のようであって、上平声十四寒(かん)韻の寒・盤・看の字が使われている。ただしこの詩は転句と結句の平仄が逆になった変格である。(即ち平起式の前2句と仄起式の後2句を合した形)
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
蘇 東坡 1036~1101
北宋の政治家・詩人・文章家。
名は軾(しょく)、字は子贍(しせん)、号は東坡。四川省眉山県の生まれ。父洵(じゅん)、弟轍とともに「唐宋8大家」に数えられ、三蘇といわれた名文章家。幼にして道教的教育を受け、20歳の時上京して官途に就く。当時の礼部侍郎(れいぶじろう)であった歐陽修(おうようしゅう)に見出され、終生師と仰ぐ。中央、地方の官を歴任しその間たびたび流謫(るたく)された。官は礼部尚書(=れいぶしょうしょ 文部科学大臣級)に至る。江蘇省常州おいて没す。散文「赤壁(せきへき)の賦(ふ)」は有名。死後皇帝より文忠公(ぶんちゅうこう)と諡(おくりな)された。享年65。
