漢詩紹介
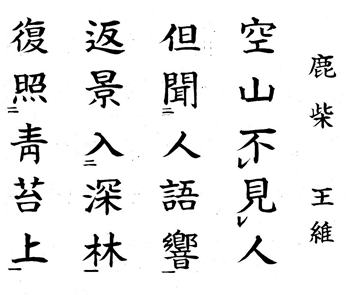
読み方
- 鹿 柴 <王維>
- 空山 人を見ず
- 但 人語の 響きを聞く
- 返景 深林に入り
- 復 青苔の 上を照らす
- ろくさい <おうい>
- くうざん ひとをみず
- ただ じんごの ひびきをきく
- へんけい しんりんにいり
- また せいたいの うえをてらす
詩の意味
人影のない、ひっそりとした山の中、誰かの話し声だけがこだまして聞こえてくる。
夕日の光が深い林の中に射し込んできて、青い苔の上をふたたび照らしている。
語句の意味
-
- 鹿 柴
- 鹿を飼うための柵「柴」は垣根
-
- 空 山
- 人影のないひっそりとした山
-
- 返 景
- 夕日の光「景」は「影」に同じ
-
- 復
- ふたたび ここでは「そして」程度
鑑賞
「動中静有り」「詩中画有り」と評される名詩
この詩は王維の別荘輞川荘(もうせんそう=A−4「竹里館」参照)を詠ずる20景の一つである。時は冬の夕暮れ。輞川荘はとんでもなく広いことを踏まえ、情景を想像してみる。周囲には小高い山が連続し、田畑がその前に広がる。比較的近くには鹿を飼う広場があって柵が設けてある。作者は苔蒸した上に生える松林の中にある小さな建物の中で、これらの風景を眺めているのではないか。そこで裴迪(はいてき)と二人で俗世を離れた閑寂の境地を楽しんでいるのである。
第一句と第二句で人語によってかえって生ずる一層の静寂さを描き、後半2句は、かすかな光によって周囲が闇であることがわかる。つまり前半が聴覚による静寂さ、後半は視覚による幽暗さを描いている。そして暗い中でつやつやと光る苔は美しい。王維の詩は「動中静有り」とか「詩中画有り」とか評されているのは、このあたりのことを言うのであろう。
備考
超有名な詩だけに多くの解説書があり、しかも少しずつ異なっているので一つの鑑賞に絞り込みにくい。特に三句日の「返景」と四句目の「復」の解釈。「返景」は「夕焼け」「夕陽」「夕陽の照り返し」など、「復」では「さらに」「また」「そして」「ふたたび」「とくに意味はない」などまちまちである。
それぞれの語によって情景や作者の本意について考えるのも深い鑑賞につながる。
参考
この詩に親友裴迪が応じた詩
-
- 日夕見寒山
- 日夕(にっせき)寒山を見る
-
- 便為独往客
- 便(すなわ)ち独往(どくおう)の客(かく)と為(な)る
-
- 不知松林事
- 松林(しょうりん)の事を知らず
-
- 但有麏か跡
- 但(ただ)麏か(かの字は鹿の下に叚)(まか)の跡(あと)有り
詩の形
五言古詩である。仄韻で上声二十二養(よう)韻の響、去声二十三漾(よう)韻の上の字が通韻して使われている。古詩は平仄を論じない。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
王維 701~761
盛唐の政治家・詩人
字は摩詰(まきつ)。山西省太原の人。開元9年(22歳)の進士。弟縉(しん)とともに幼少より俊才。55歳の時、安禄山の乱に遭遇し、賊にとらえられ偽官の罪を得たが、のち赦される。59歳で官は尚書右丞(しょうしょゆうじょう)に至る。晩年はこれまでの役人生活に疑問を抱き、輞川に隠棲し、詩・書・画・楽に専念する生活を送った。兄弟ともに仏門に帰依(きえ)する。また画の名手として南宗画(水墨を以って描く文人画)の祖となる。仏道に深い信仰心をもった詩人であるから後世「詩仏」と称えられている。享年61。
