漢詩紹介
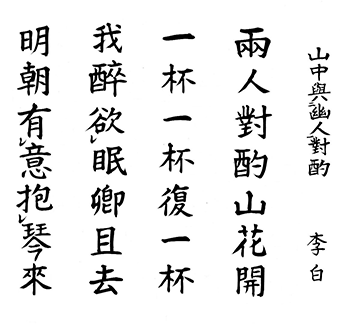
読み方
- 山中幽人と対酌す <李白>
- 両人対酌 山花開く
- 一杯 一杯 復一杯
- 我酔うて眠らんと欲す 卿且く去れ
- 明朝 意 有らば 琴を抱いて来たれ
- さんちゅうゆうじんとたいしゃくす <りはく>
- りょうにんたいしゃく さんかひらく
- いっぱい いっぱい またいっぱい
- われよオてねむらんとほっす きみしばらくされ
- みょうちょう い あらば ことをいだいてきたれ
詩の意味
花の咲いている山中で、君と私は向き合いながら、世俗のことを忘れて酒を酌み交わす。一杯、一杯、また一杯と。
私はすっかり酔って眠くなったので、君はひとまず帰りたまえ。明朝気が向いたら今度は琴を抱えて話に来てくれ。
語句の意味
-
- 幽 人
- 隠者 世俗を離れ奥深い所などに住む人
-
- 卿
- 同等以下に用いる二人称
-
- 且
- 少しの間 まあちょっと ひとまず
-
- 琴
- 膝の上に乗るほどの琴
鑑賞
いらぬ気遣いせぬ自由人・李白
この詩は作者56歳の7月、廬山に隠棲したころの作とする説もあるが不詳である。玄宗に追われて十二、三年を経たころの作と思われる。題名通り山中で気持ちよく幽人と酒を酌み交わした折の気持ちを詠った詩である。
承句の「一杯一杯復一杯」の句は、何の熟慮もない、むしろ大詩人らしからぬ表現だが、俗世間から逃れるには酒しかないと素直に言い放ったところが“酒仙”李白らしい。酒好きな者にとっては思わずニンマリとさせられる。作詩法としては同字重出でよくないが、かえってリズム感があり、軽快な詩になっている。
転句は「宋書・陶淵明伝」に「貴賤の之に造(いた)る者、酒有らば輒(すなわ)ち設く。淵明、若し先に酔はば、便ち客に語りて曰く、『我酔いて眠らんと欲す、卿、去るべし』と。其の真率(しんそつ=率直で飾り気のないこと)此の如し」とあるに基づく。何かにつけて陶淵明を借用していることは「山中問答」の項でも述べた通りである。
結句も幽人としての立場から鑑賞したい。自分だけが酔眠を望み、客人にはもう帰ってくれと言うのは、いささか失礼な接客態度ではないかと思うが、自由を楽しむ、同じ幽人だからこそ分かり合える親しみの表現ととりたい。客人も李白と琴を楽しむために、きっと翌日もやって来たであろう。
「山中問答」「独り敬亭山に坐す」とともに離俗の詩の三部作といってもよく、有名な詩である。
参考
「唐詩選」にはなく「古文真宝前集」に所収されている。また題名を「山中対酌」とするものもある。
詩の形
平起こり七言絶句の形のようであるが、起句が下三連、承句が二四同、二六不同になっているから拗体である。
さらに承句の同語の繰り返しは作詩法にない型破りである。上平声十灰(かい)韻の開、杯、来の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
李 白 701~762
盛唐時代の詩人
四川省の青蓮(せいれん)郷の人といわれるが出生には謎が多い。若いころ任侠の徒と交わったり、隠者のように山に籠ったりの暮らしを送っていた。25歳ごろ故国を離れ漂泊しながら42歳で長安に赴いた。天才的詩才が玄宗皇帝にも知られ、2年間は帝の側近にあったが、豪放な性格から追放され、再び漂泊した。安禄山の乱後では反朝廷側に立ったため囚われ流罪(るざい)となったがのち赦(ゆる)され、長江を下る旅の途上で亡くなったといわれている。あまりの自由奔放・変幻自在の性格や詩風のためか、世の人は「詩仙」と称えている。酒と月を愛した。享年62。
