漢詩紹介
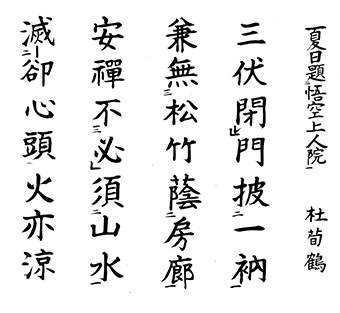
読み方
- 夏日悟空上人の院に題す <杜荀鶴>
- 三伏門を閉じて 一衲を披く
- 兼ねて松竹の 房廊を蔭う無し
- 安禅は必ずしも山水を須いず
- 心頭を滅却すれば 火も亦涼し
- かじつごくうしょうにんのいんにだいす <とじゅんかく>
- さんぷくもんをとじて いちのうをひらく
- かねてしょうちくの ぼうろうをおおオなし
- あんぜんはかならずしも さんすいをもちいず
- しんとうをめっきゃくすれば ひもまたすずし
詩の意味
暑さの厳しい三伏の時期に、悟空上人は門を閉ざして僧衣をきちんと着ている。その上、強い日差しから住まいを蔭ってくれる松や竹の樹木もない。
しかし、座禅をして修行に励むには、必ずしも山や川を必要としない。暑いと思う心を消しされば、火でさえ自然と涼しく感じられるものである。
語句の意味
-
- 悟空上人
- 人物は不詳
-
- 三 伏
- 夏至の後3番目の庚(かのえ)の日を初伏(しょふく=今の7月中旬)4番目を中伏(同7月下旬)立秋後の最初の庚の日を末伏(同8月初旬)といいあわせて三伏と呼ぶ 暑さの最も厳しい時期
-
- 一 衲
- 一着の僧衣
-
- 房 廊
- 「房」は部屋 「廊」は廊下 住まい
-
- 安 禅
- 座禅をして雑念をなくす 夏安居座夏(げあんござげ)といって夏にする座禅がある
鑑賞
名訓「心頭を滅却すれば火も亦涼し」
夏の暑さにも無心に耐えている悟空上人に贈った詩。作者が禅宗に入門したという記録はないが、深く禅宗に関心があったので、その道の老師である悟空上人に憧れつつ少しでも近づきたいという心が読み取れる。「三伏」「一衲」「安禅」を除けば衆人にもわかる表現である。それにしても、第4句は現代人には及びもつかない精神である。暑ければ冷房で、寒ければ暖房で過ごすのが当たり前の時代だから、火の中でも涼しいと言われれば、あの世の世界のことではないかと思われてしまう。しかしその精神は尊い。第4句は「心中を滅し得たれば火自ずから涼し」もある。この句は現在では、いかなる苦難に遭っても、精神の持ち方次第では何ら苦難を感じないの意味に使われている。修身の名言である。
備考
この詩の第3句と第4句は古来より有名な句で、京都の東福寺の福嶋俊翁(ふくしましゅんおう)老師の教示によれば、禅家の「碧巌(へきがん)集」の第43則「洞山無寒暑(どうざんむかんしょ)」の話の中にも引用されている。織田信長が天正10年(1582)に甲斐の恵林寺を火攻めにした時、快川和尚は衆僧とともに楼門に上がり、この句を誦しながら焼死したなどの逸話がある。
参考
禅宗とは
簡単に説明できるものではないが概略だけ記してみる。
一言でいえば坐禅を最も大切と考える人々の集まりといえる。インドから中国に来た達磨大師を祖とする。宋代に臨済・曹洞・潙仰・雲門・法眼の5派に分裂、さらにその後臨済が2派に分裂した。日本には鎌倉時代までにそれらすべての派が伝わったが、今日では臨済・曹洞の2派が存続する。
宗派 開祖 主たる信者 主たる寺院
臨済宗 栄西 上級武士 建仁寺(京都)
曹洞宗 道元 地方武士・農民 永平寺(福井)
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声七陽(よう)韻の廊、涼の字が使われている。起句は踏み落としである。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
杜荀鶴 846~904
晩唐の詩人
字は彦之。号は九華山人。池州(安徽省)の人。大順2年(891)46歳でようやく進士に及第し、翰林学士(かんりんがくし)、主客員外、知制誥(ちせいこう)などを歴任した。伝説では杜牧の末っ子といわれている。軽薄な性格とも評されているが、詩を作るのが巧みで、「滄浪詩話」ではその詩体を杜荀鶴体と呼んでいる。唐末の戦乱に苦しむ民衆の惨苦(さんく)を詠いながら塵濁(じんだく)を逃れて禅の境地に入ろうとする傾向がみられる。「唐風集」3巻がある。享年58。
