漢詩紹介
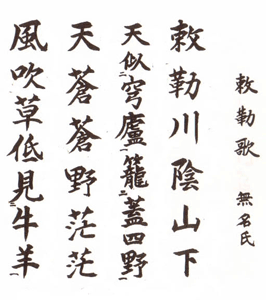
読み方
- 勅勒の歌 <無名氏>
- 勅勒の川 陰山の下
- 天は穹盧に似て 四野を籠蓋す
- 天は蒼蒼 野は茫茫
- 風吹き草低れて 牛羊見わる
- ちょくろくのうた <むめいし>
- ちょくろくのかわ いんざんのもと
- てんはきゅうろににて しやをろうがいす
- てんはそうそう のはぼうぼう
- かぜふきくさたれて ぎゅうようあらわる
詩の意味
勅勒の草原は陰山山脈のふもとに横たわり、大空はパオのように四方の平野におおいかぶさっている。
空はどこまでも青く、野原は果てしなく広がり、風が吹いて草が低くなびくと、平原のあちこちには放牧された牛や羊の姿が現れる。
語句の意味
-
- 勅勒歌
- 今の甘粛省(かんしゅくしょう)から内蒙古一帯にすんでいた勅勒族の民謡
-
- 勅勒川
- 勅勒族が遊牧する草原 「川」は山と山の間の平地
-
- 陰 山
- 陰山山脈 中国と蒙古との境界をなす山脈
-
- 穹 盧
- 遊牧民が用いた天井の丸いテント(パオ・ゲル)
-
- 籠 蓋
- おおいかぶさる 「籠」はこめる 「蓋」はおおう
-
- 見
- 「現」と同じで現れる 見えてくる
鑑賞
遊牧民の大自然を歌う
この詩は1句の文字数がふぞろいであり、韻の踏み方も不規則である。最初の2句の素朴な表現が、中国のはるか北方の果てしなく広がる雄大な天地の景色をよく映している。スケッチ風におおづかみに描写した後、後半では天空を円屋根と見なす着想がおもしろく、これに色彩を加え、風になびく草や牛羊などを配して動きを与えている。単調な実景を映し、強いひびきを持つこの詩は一幅の絵画をしのぐものがあり、また六朝時代の名作の名に恥じないものがある。
備考
この詩は勅勒地方で歌われていた民謡であるといわれるが、一説に北斉の斛律金(こくりつきん)の作ともいわれるが不明である。
勅勒川 陰山下 天似穹廬 籠蓋四野 天蒼蒼 野茫茫 風吹草低 見牛羊
この詩は、白話文学史の中で、もと鮮卑(外蒙古やシベリアにいたトルコ系の遊牧民族)という種族の民謡であったが、北斉(6世紀)の時代に漢訳されたものといわれる。
宋の郭茂倩(かくもさい)の「楽府詩集」にある楽府の解題の書「楽府広題」によると、斉の神武帝高歓が、北周(山西省)を攻めて失敗し多くの兵を失い、また自分も病を患った。周王の宇文泰は軍に布告し「高歓の馬鹿者が兵を率いて玉壁に侵入してきたが、一戦を交えただけで自分から斃(たお)れた」と言った。それを聞いた高歓は病をおして座り、士衆を安心させ、また武将を集めて、部下の斛律金(488~567)にこの詩を歌わせ自らも唱和して、部下の士気を奮い立たせたという。当時広く軍中に歌われていたと思われる。
漢詩の小知識
「見」のいろいろ
-
- みル
- 見学 一見
-
- みエル
- 外見 散見
-
- まみエル
- 謁見 引見 参見
-
- あらわル
- 露見
-
- しめス
- 見示
出典
「楽府詩集」宋・郭茂倩編
詩の形
仄起こりの雑言古詩の形であって、上声二十一馬(ま)韻の下、野と、下平声七陽(よう)韻の茫、羊の字が使われ、変則的な形式である。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||
 |
作者
不明
