漢詩紹介
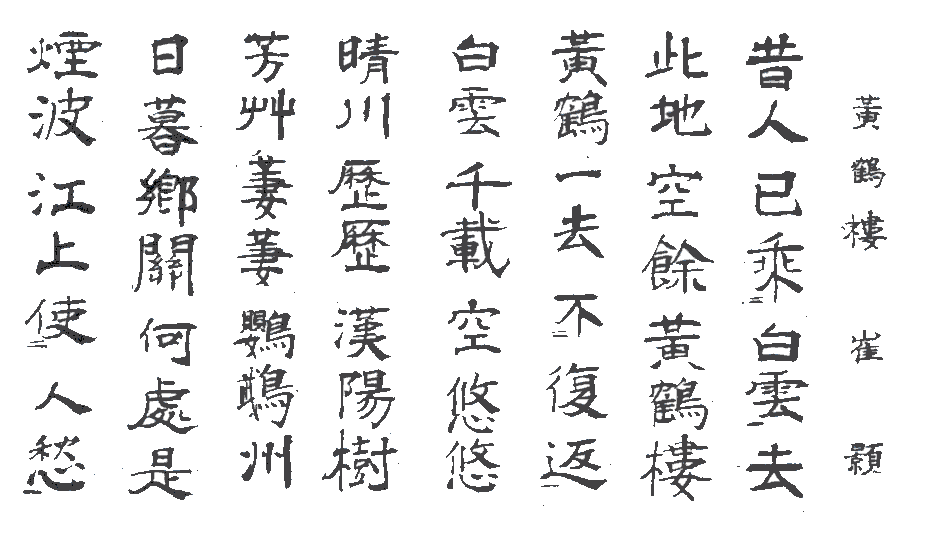
読み方
- 黄鶴樓<崔顥>
- 昔人已に 白雲に乗じて去り
- 此の地空しく餘す 黄鶴樓
- 黄鶴一たび去って 復返らず
- 白雲千載 空しく悠悠
- 晴川歴歴たり 漢陽の樹
- 芳艸萋萋たり 鸚鵡洲
- 日は暮れて郷關 何れの処處か是なる
- 煙波江上 人をして愁しましむ
- おうかくろう<さいこう>
- せきじんすでに はくうんにじょうじてさり
- このちむなしくあます おうかくろう
- おうかくひとたびさって またかえらず
- はくうんせんざい むなしくゆうゆう
- せいせんれきれきたり かんようのじゅ
- ほうそうせいせいたり おうむしゅう
- ひはくれてきょうかん いずれのところかこれなる
- えんぱこうじょう ひとをしてかなしましむ
字解
-
- 黄鶴樓
- 湖北省武漢市長江南岸蛇山の西端にある楼閣。昔、この地に辛(しん)という酒店があった。毎日のように老人が来て酒を飲んでゆく。酒代は払わないが辛はいやな顔もせず飲ませていた。半年程して老人は酒代の代わりにといって橘の皮で黄色い鶴を描き、その鶴が客の歌にあわせて踊りだすというので評判になり店は大繁盛。辛は巨満の富を築いた。十年ののち老人が再び現れ、笛を吹くと白雲が湧きおこり、老人は鶴に乗って飛び去った。辛はここに楼を建て黄鶴樓と名づけたという伝説がある。
-
- 悠 悠
- 遥(はるか)な大空を流れていくさま ゆったりとしているさま
-
- 歴 歴
- はっきりとみえること
-
- 漢 陽
- 武昌より長江を隔(へだ)てた対岸にある地名
-
- 萋 萋
- 草の盛んに茂るさま
-
- 鸚鵡洲
- 武昌の西南の長江にある中洲
-
- 煙 波
- 夕もや
意解
昔の仙人は已に白雲とともに黄鶴に乗って去り、この地にはただ黄鶴樓が残っているばかりである。
一度去った仙人の乗った黄鶴は再び帰っては来ず、白雲のみが千年も昔のままゆったりと浮かんでいる。
(この楼から望めば)晴れ渡った川の景色ははっきりとして、対岸の漢陽の樹色が見え、草の盛んに茂っている鸚鵡洲も近くに見える。
《だが自分は天涯に漂泊(ひょうはく)の身》日暮れになると郷里はどちらの方角にあたるかと思われ、夕もやが立ち込める長江の風情(ふぜい)が私を悲しませるのである。
備考
この詩の構造は、平起こり七言律詩の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の樓、悠、洲、愁の字が使われている。第一句は踏み落としになっており、四字目が孤平、第三句は二四同仄で仄下三連、第四句は平下三連等、平仄は七言律詩としては破格であるが、唐代七言律詩の第一として「唐詩三百首」「唐詩選」に所収されている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
崔 顥 704-754
盛唐の詩人。「水卞」洲(べんしゅう)《河南省開封府》の人。開元11(723)年の進士、秀才であったが酒と遊びに溺れ軽薄の評をうけた。晩年は格調の高い詩風を出す。天宝13年に没す。年50。
