漢詩紹介
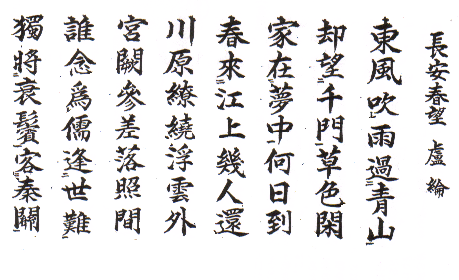
読み方
- 長安春望<盧綸>
- 東風雨を吹いて 青山を過ぐ
- 却って千門を望めば 草色閑なり
- 家は夢中に在って 何れの日か到らん
- 春は江上に來りて 幾人か還る
- 川原繚繞す 浮雲の外
- 宮闕參差たり 落照の間
- 誰か念わん儒と爲りて 世難に逢い
- 獨り衰鬢を將て 秦關に客たらんとは
- ちょうあんしゅんぼう<ろりん>
- とうふうあめをふいて せいざんをすぐ
- かえってせんもんをのぞめば そうしょくかんなり
- いえはむちゅうにあって いずれのひかいたらん
- はるはこうじょうにきたりて いくにんかかえる
- せんげんりょうじょうす ふうんのほか
- きゅうけつしんしたり らくしょうのかん
- たれかおもわんじゅとなりて せなんにあい
- ひとりすいびんをもって しんかんにかくたらんとは
字解
-
- 東 風
- 春風
-
- 千 門
- 宮城の多くの門
-
- 繚 繞
- めぐりめぐる くねくねと曲っている形容
-
- 宮 闕
- 宮殿
-
- 參 差
- 高く低くふぞろい
-
- 落 照
- 夕日の光
-
- 世 難
- 世の中の騒乱
-
- 衰 鬢
- 薄くなった鬢の毛
-
- 秦 關
- 関中 ここでは長安をさす
意解
春風が雨を吹きおくりつつ青い山なみを過ぎてゆく。ふりかえって、数多い宮城の門の方角をみわたせば茂った若草の色はのどかである。
故郷の家は、夢に見るばかりでいつになったら帰ることができようか。春はいま川のほとりにやって来たが故郷に帰れる人は幾人あるだろう。
川ぞいの原野はくねくねと浮き雲のかなたまで続き、宮殿は高くあるいは低く夕日の光をあびて輝いている。
ああ、儒者としてこの乱世にめぐりあわせ、髪の毛も薄くなった老いの身で、たったひとり秦関に旅暮らししようとは、いったい誰が思ったことだろう。
備考
この詩は、長安の春景色を眺めながら、自分の不遇を悲しんで作る。一説に大暦初年、科挙に落第しつづけた頃の作といわれるが、大暦初年は30歳位で衰鬢には当らないので、もっと後の作であろうと思われる。「唐詩選」に所収されている。
詩の構造は、平起こり七言律詩の形であって、上平声十五刪(さん)韻の山、閑、還、間、關の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
盧 綸 748-800?
中唐の詩人。字は允言(いんげん)。山西省永済県の人。安禄山の乱をさけて<番+おおざと>陽(はよう)に移り、何度も進士(高等文官)の試験を受けたが失敗した。その後宰相の元載(げんさい)にその才能を認められ、河南首閔(しゅみん)郷の尉(軍事・警察を司る)となり、昇進して監察御史(官僚の功罪を監察する官)となったが、病気のため辞職して故郷に帰った。「盧戸部(ろこふ)詩集」10巻がある。
