漢詩紹介
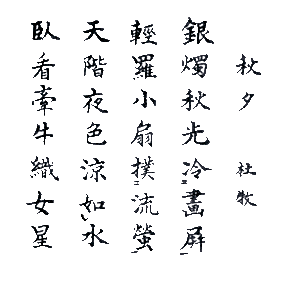
吟者:稲田 菖胤
2005年3月掲載
読み方
- 秋夕<杜牧>
- 銀燭秋光 畫屏冷ややかなり
- 輕羅小扇 流螢を撲つ
- 天階の夜色 涼水の如し
- 臥して看る牽牛 織女の星
- しゅうせき<とぼく>
- ぎんしょくしゅうこう がへいひややかなり
- けいらしょうせん りゅうけいをうつ
- てんかいのやしょく りょうみずのごとし
- ふしてみる けんぎゅう しょくじょのほし
字解
-
- 銀 燭
- 銀の燭台
-
- 畫 屏
- 絵をかいた屏風(びょうぶ)
-
- 輕 羅
- うすい絹を張った「うちわ」
-
- 流 螢
- 流れるように飛ぶほたる
-
- 天 階
- 一本に「天街」とあり、天階は天子の宮殿の階段をいい、宮中という意である
-
- 臥 看
- 寝たままで仰ぎみるさま
-
- 牽牛織女星
- 年に一回たなばたの夜、天の川をへだてて会うという彦星と織姫
意解
白銀色の秋の夜のともしびの光が、彩(いろど)り豊かな絵屏風に冷たく照り映え、宮女がひとりうすい絹の団扇(うちわ)で小さくうちながら、飛び交う螢とたわむれている。
天上の夜空のようすは、水のように涼しくみえて、その宮女は寝ながら牽牛(けんぎゅう)星と織女(しょくじょ)星をみつめつづけてばかりいる。
備考
君に寵(めぐ)みを得ない宮女が、二つの星が一年に一度ずつでも相遇(あいあ)うことを羨んでいる情を写したものである。流螢を打ち、七夕星を仰ぎつつ、こぬ人を待ちわびる宮中の美女の姿態あらわには描かずして一幅(いっぷく)の人物画を完成させた手法がみられる詩である。
この詩の構造は仄起こり七言絶句の形であって、下平声九青(せい)韻の屏、螢、星の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
杜 牧 803-853
晩唐の詩人、字(あざな)は牧之(ぼくし)、号は樊川(はんせん)、京兆万年(けいちょうばんねん)〔陝西省長安県(せんせいしょうちょうあんけん)〕の人。名家の出身にして828年進士(しんし)に及第後、地方、中央の官を歴任し中書舎人(ちゅうしょしゃじん)となって没す。資性剛直、容姿美しく歌舞を好み、青楼に浮名を流したこともあった。樊川文集二十巻、樊川詩集七巻あり、阿房宮賦(あぼうきゅうふ)は早年の作にして文名を高めた。年50。
