漢詩紹介
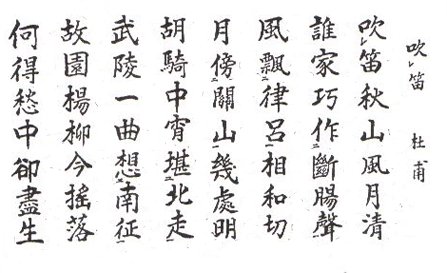
読み方
- 笛を吹く<杜甫>
- 笛を吹く秋山 風月の清きに
- 誰が家か巧みに 斷腸の聲を作す
- 風は律呂を飄して 相和すること切に
- 月は關山に傍うて 幾處か明らかなる
- 胡騎中宵 北走するに堪えたり
- 武陵の一曲は 南征を想う
- 故園の楊柳は 今搖落す
- 何ぞ得ん愁中 卻って盡く生ずるを
- ふえをふく<とほ>
- ふえをふくしゅうざん ふうげつのきよきに
- たがいえかたくみに だんちょうのこえをなす
- かぜはりつりょをひるがえして あいわすることせつに
- つきはかんざんにそうて いくしょかあきらかなる
- こきちゅうしょう ほくそうするにたえたり
- ぶりょうのいっきょくは なんせいをおもう
- こえんのようりゅうは いまようらくす
- なんぞえんしゅうちゅう かえってことごとくしょうずるを
字解
-
- 斷腸聲
- 聞く人の腸をかきむしるような悲しい声
-
- 律 呂
- 音楽の調子を陰陽の二つに分け陰を呂(六呂=りくりょ) 陽を律(六律=りくりつ)という
-
- 關 山
- 国境にある山
-
- 中 宵
- 真夜中
-
- 胡騎北走
- 唐代 北方または西方の異民族を胡(えびす)と呼んだ 晋の将軍劉〈王昆〉(りゅうこん=270ー318)が并州(へいしゅう)を孤立無援で堅く守り 月のさえた夜城楼に上り胡笳を吹いたところ 胡軍はその悲しみに涙を流し北の故郷へ帰り去ったという故事
-
- 武陵一曲
- 後漢(ごかん)の馬援(ばえん=前14ー49)が交趾(こうし=現ベトナム)の蛮族を征服した後 武陵(湖南省北部)に遠征した時 部下の笛に合せて 僻地(へきち)遠征の寂寥の歌を詠んだ この歌を「武陵深行(ぶりょうしんこう)」という
意解
秋の山の風も月も清らかにさえわたる夜、笛の音が聞こえてくる。誰がこれほど巧みに、人の腸をかきむしるように物悲しい音を吹きならすのだろうか。
風は律呂の響きをひるがえして調和もとれ、月は関山によりそうて、幾つかの峰にさえわたっている。
このような笛の音を聞けば、晋の劉〈王昆〉の故事のように、手荒い胡の兵も悲しみに堪え切れず、夜中に北方の故郷へ逃げ去ったであろう。また後漢の馬援が武陵に遠征した時、部下の曲に合せて歌った「武陵深行」という曲もこのように悲しいものであったろうか。
故郷の柳も秋になって葉も落ちつくしたであろう。それなのに今巧みな「折楊柳」の曲をきくと、愁いにふさがる私の胸の中に緑の柳の芽を出させ、その枝を折って別れのなげきをくり返すことが出来ようか。
備考
杜甫は、765年成都を去り、768年夔州(きしゅう=現在の奉節県)に移り、その年の秋に哀れな笛の音を聞いてこの詩を作る。杜甫55歳の作。「唐詩選」に所収されている。
詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の清、聲、明、征、生の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
杜 甫 712-770
盛唐の詩人で李白と並び称せられ、中国詩史の上での偉大な詩人である。字は子美(しび)。少陵(しょうりょう)または杜陵と号す。洛陽に近い鞏県(きょうけん)の生まれ、7歳より詩を作る。各地を放浪し生活は窮乏を極め、安禄山の乱に賊軍に捕らわれる。律詩に巧みで名作が多い。湖南省潭州(たんしゅう)から岳州に向かう船の中で没す。年59。李白の詩仙に対して、杜甫は詩聖と呼ばれる。
