漢詩紹介
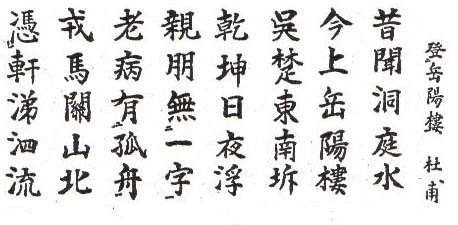
吟者:岸本快伸・古賀千翔
2010年6月掲載
読み方
- 岳陽樓に登る<杜甫>
- 昔聞く 洞庭の水
- 今上る 岳陽樓
- 呉楚 東南に坼け
- 乾坤 日夜浮かぶ
- 親朋 一字無く
- 老病 孤舟有り
- 戎馬 關山の北
- 軒に憑って 涕泗流る
- がくようろうにのぼる<とほ>
- むかしきく どうていのみず
- いまのぼる がくようろう
- ごそ とうなんにひらけ
- けんこん にちやうかぶ
- しんぽう いちじなく
- ろうびょう こしゅうあり
- じゅうば かんざんのきた
- けんによって ていしながる
字解
-
- 岳陽樓
- 湖南省洞庭湖東北岸の町岳州にある 唐の開元4年(716)に建てられた 文人墨客の詩文が多く飾られている
-
- 昔 聞
- 昔から聞いている 「昔・今」の対応は時の推移に伴う事態の変転をのべる語法
-
- 呉 楚
- 春秋戦国時代の呉と楚 呉は今の江蘇省のうち揚子江以南の地 楚は今の湖南・湖北両省の地
-
- 坼
- 二つにひきさく
-
- 乾 坤
- 天と地 蒼々とひろがる天と広々と横たわる大地
-
- 無一字
- 一通の手紙も届かない
-
- 戎 馬
- 兵馬 戦争
-
- 關 山
- 関所のある山 国境にある山
-
- 涕 泗
- 涙 「涕」は泣くとき目から出る涙 「泗」は涙とともに鼻から出る汁
意解
昔から洞庭湖の壮観は話に聞いていたが、今初めて岳陽楼に上(のぼ)って見わたすことになった。
呉・楚の地は国土の東南部でこの湖によって二つにひきさかれ、はてしなく広がる水の面には天地が日夜浮動している。
さて、今の私には親戚朋友からは一通の便りもなく、老病のわが身には一そうの小舟があるだけである。
思えば、今なお戦乱が関所のある山の北の故郷ではつづいている。それを思いつつ手すりに寄りかかっていると涙が流れおちるばかりである。
備考
768年夔州(きしゅう=現在の奉節県)を去り最後の放浪の旅に出た杜甫は、三峡を下って江陵に至り更に洞庭湖の岳陽にたどりつき船をとめてこの楼に遊んだ時に作る。
「唐詩選」「唐詩三百首」に所収されている。この詩の構造は平起こり五言律詩の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の樓、浮、舟、流の字が使われている。第一句は二四不同になっていない。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
杜甫 712-770
盛唐の詩人で李白と並び称せられ、中国詩史の上での偉大な詩人である。字は子美(しび)。少陵(しょうりょう)または杜陵と号す。洛陽に近い鞏県(きょうけん)の生まれ、7歳より詩を作る。各地を放浪し生活は窮乏を極め、安禄山の乱に賊軍に捕らわれる。律詩に巧みで名作が多い。湖南省潭州(たんしゅう)から岳州に向かう船の中で没す。年59。李白の詩仙に対して、杜甫は詩聖と呼ばれる。
