漢詩紹介
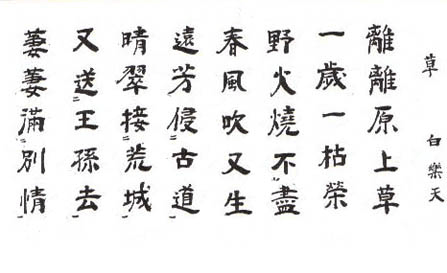
読み方
- 草<白樂天>
- 離離たり 原上の草
- 一歳に 一たび枯榮す
- 野火 燒けども 盡きず
- 春風 吹いて 又生ず
- 遠芳 古道を侵し
- 晴翠 荒城に接す
- 又王孫の 去るを送れば
- 萋萋として 別情滿つ
- くさ<はくらくてん>
- りりたり げんじょうのくさ
- いっさいに ひとたびこえいす
- やか やけども つきず
- しゅんぷう ふいて またしょうず
- えんぽう こどうをおかし
- せいすい こうじょうにせっす
- またおうそんの さるをおくれば
- せいせいとして べつじょうみつ
字解
-
- 離 離
- 草がつやつや生い繁っているさま ならび連っているさま
-
- 一 歳
- 1年
-
- 枯 榮
- 枯れたり繁ったり
-
- 野 火
- 野原で枯草を燃やす火 のび
-
- 遠 芳
- 遠くにつづく草の香り
-
- 晴 翠
- 晴れた草原の緑色
-
- 荒 城
- 荒れ果てた城壁
-
- 王 孫
- 王者の子孫 貴公子
-
- 萋 萋
- 草や木のしげっているさま
-
- 別 情
- 離別の情
意解
つやつやと生い繁っている野原の草は、1年に1度枯れたり、繁ったりしている。
野原で枯草を燃やしても、その根は尽きることがなく、春風の吹くころにはまた芽を出してくる。
遠くにつづく草の香りは、古い道にまでただよい、晴れた日の草の緑色は、荒れはてた城壁に連なっている。
またも王者の子孫が旅立つのを送るのであるが、草の生い茂る中に、離別の悲しみの情が胸一ぱいあふれてくるのである。
備考
この詩は787年白樂天16歳の作とされ「唐詩三百首」に所収されている。「長慶集」には「賦得古原草送別」となっており、草という詠物体に送別の意をからめた詩であり、本会では「草」と簡略にした。
詩の構造は平起こり五言律詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の榮、生、城、情の字が使われている。第三句は二四不同になっていない。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
白樂天 772-846
中唐の大詩人。名は居易(きょい)、字は樂天、号は香山居士(こうざんこじ)。陝西(せんせい)省渭南(いなん)の人、太原(たいげん)の人(山西省)ともいう。家は代々官吏。早くから詩を作り、16歳「春草の詩」17歳「王昭君」の作あり。貞元(ていげん)16年(800)進士。元稹(げんしん)と親交あり。江西省九江の司馬に左遷されたこともあるが、ほぼ中央の官にあり、刑部尚書(ぎょうぶしょうしょ)にて没す。年75。「長恨歌」(ちょうごんか)「琵琶行」(びわこう)の大作あり。「白氏長慶集」(はくしちょうけいしゅう)「白氏文集」(はくしもんじゅう)など我が国にも伝わり、平安文学に感化影響を与えた。
