漢詩紹介
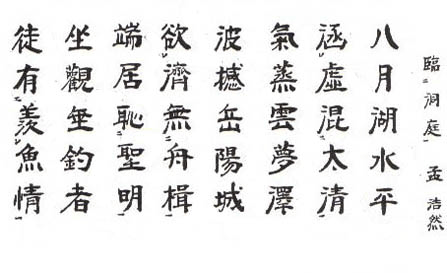
読み方
- 洞庭に臨む<孟浩然>
- 八月 湖水平らかなり
- 虚を涵して 太清に混ず
- 氣は蒸す 雲夢澤
- 波は撼かす 岳陽城
- 濟らんと欲するに 舟楫無し
- 端居して 聖明に恥ず
- 坐して觀る 垂釣の者
- 徒に魚を 羨むの情有り
- どうていにのぞむ<もうこうねん>
- はちがつ こすいたいらかなり
- きょをひたして たいせいにこんず
- きはむす うんぼうたく
- なみはうごかす がくようじょう
- わたらんとほっするに しゅうしゅうなし
- たんきょして せいめいにはず
- ざしてみる すいちょうのもの
- いたずらにうおを うらやむのじょうあり
字解
-
- 涵 虚
- 「涵」はひたす 水につける うるおす 「虚」は大空
-
- 混太清
- 「太清」は天の一番高いところ 「混」はとけあう
-
- 氣 蒸
- たちのぼる水気
-
- 雲夢澤
- 雲夢の地方にある大湿地帯 昔 楚の国にあった大きな湖沼 現在湖北省に多くある湖はその遺跡
-
- 岳陽城
- 湖北省岳陽の町 洞庭湖の東北に位置する
-
- 舟 楫
- 舟とかじ ここでは天子の政治を助ける臣下
-
- 端 居
- 何もしないでぶらぶらしていること
-
- 聖 明
- すぐれた天子
-
- 坐 觀
- 「坐(そぞろ)に観(み)る」とも読む
-
- 羨魚情
- 魚が欲しいと羨む気持ち 「漢書董仲抒(とうちゅうじょ)伝」に「淵に臨んで魚を羨むは 退いて網を結ぶに如かず」に基づく
意解
旧暦の8月洞庭湖の水は満々とみなぎり、水平線の彼方と、天の一番高い大空ととけあい一つになっている。
立ちのぼる水気は、雲夢の大湿地帯までわたって立ちこめ、打ちよせる波は、洞庭湖の東北にある岳陽城をゆり動かしている。
湖水を濟(わた)ろうとしても舟や楫(かい)もない、(政治を補ける任につき、役人になって働きたいが引立ててくれる者もない)何もせず聖天子の治めておられる太平の世にぼんやりとしている事を恥ずかしく思うばかりである。
ここに坐って湖水に釣りをしている人を見ていると、自分も魚が欲しいと羨む気持がわいてくる。(希望を抱くだけで何もしないよりは、仕事をするべく仕官したい気持がわいてくる)
備考
この詩は洞庭湖の壮大な風景を前にして、感慨をのべたものである。「臨洞庭上張丞相」が本題であるが、本会は「臨洞庭」と簡略にした。「唐詩選」「唐詩三百首」に所収されている。
詩の構造は仄起こり五言律詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の平、清、城、明、情の字が使われている。第一句は二・四不同になっていない。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
孟浩然 689-740
盛唐の詩人で名は浩、字は浩然。五言詩にたくみで、自然詩人として王維とならび称せられる。湖北省襄陽の人で土地の豪族。若くして義侠心にとみ、40歳にして都長安に出て王維、張九齢と交わるも、官につかず殆んど郷里で山林の閑寂(かんじゃく)にひたって過ごした。52歳病のため没す。「孟浩然集」4巻あり。
参考
洞庭湖
洞庭湖は長江の南、湖南省にあり江西省のハヨウ湖に次ぐ中国第二の淡水湖である。面積は渇水期で約3000平方キロメートル、増水期には約4000平方キロメートル(東京都の倍の大きさ)ある。湖周の名勝を綴った瀟湘(しょうしょう)八景が日本の近江八景のもとといわれる。
