漢詩紹介
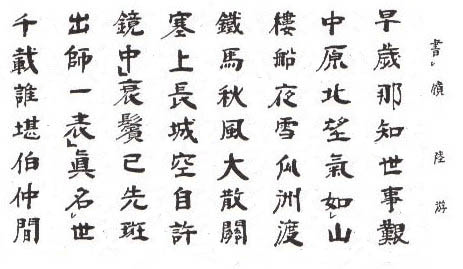
読み方
- 憤りを書す<陸游>
- 早歳那ぞ知らん 世事の艱きを
- 中原北望して 氣 山の如し
- 樓船夜雪 瓜洲の渡
- 鐵馬秋風 大散關
- 塞上の長城 空しく自ら許すも
- 鏡中の衰鬢 已に先ず斑なり
- 出師の一表 眞に世に名あり
- 千載誰か堪えん 伯仲の間
- いきどおりをしょす<りくゆう>
- そうさいなんぞしらん せじのかたきを
- ちゅうげんほくぼうして き やまのごとし
- ろうせんやせつ かしゅうのわたし
- てつばしゅうふう だいさんかん
- さいじょうのちょうじょう むなしくみずからゆるすも
- きょうちゅうのすいびん すでにまずまだらなり
- すいしのいっぴょう まことによになあり
- せんざいたれかたえん はくちゅうのかん
字解
-
- 早 歳
- 若いころ
-
- 樓 船
- 二階づくりの大船(船戦に用いる樓艦)
-
- 瓜 洲
- 江蘇省江都県の南にあった地名 大運河の入り口にあたる要衝の地
-
- 鐡 馬
- 武装した馬
-
- 大散關
- 陝西(せんせい)省宝鶏(ほうけい)県の南西の隴山(ろうざん)にある関所 当時は宋と金との境界をなしていた
-
- 塞上長城
- 北辺の国境にある万里の長城
-
- 出師一表
- 諸葛孔明の出師の表をいう(前後二編あり) 三国時代の蜀の名宰相諸葛孔明が魏との戦いに出兵するにあたって蜀の天子劉禪に奉った文
-
- 伯仲間
- 伯は兄 仲は弟 ここでは優劣の差のないこと
意解
若いころの私には、どうして世の中のけわしさなどがわかろうか。中原の地をはるか北に望んで、意気は山のように盛んであった。
そのためかつてはやぐらを組んだ軍船にのって雪の夜瓜洲(かしゅう)の渡し場を過ぎたこともあり、秋風の冷たく吹く中を軍馬を駆けらし国境の大散関に行ったこともあった。
身をていして辺境の長城となって国を守ろうと自ら出むいたが今は空しい夢となり、鏡にうつる鬢の毛もすでに衰えて白くなってしまった。
諸葛孔明の書いた「出師の表」こそは、真に孔明の忠誠心を一世にとどろかしたものであるが、千年たった今日まで果たしてこれに伯仲する人物があらわれただろうか。
備考
1161年、瓜洲渡、大散関はそれぞれ重要拠点であった。金国(きんこく)の軍がこれを占領したが、翌年陸游も作戦に参加して奪回した。
老いてゆく自分を悲しみながら、孔明のような忠臣を得て宋再興の業を成しとげたいという思いからこの詩を作る。この詩の構造は仄起こり七言律詩の形であって、上平声十五刪(さん)韻の艱、山、關、斑、間の字が使われている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
陸 游 1124-1209
中国南宋前期の人。号は放翁、官職に在り、詩人として南宋四大家(揚万里・范成大・尤袤=ゆうぼう)の随一とされる。32歳から85歳の死に至るまでの50年間の詩作「剣南詩稿」85巻をのこし、総数一万首、晩年多作にして、その詩ことごとく充実する。愛国の詩人として常に北方平定を願っていたが果たされなかった。
