漢詩紹介
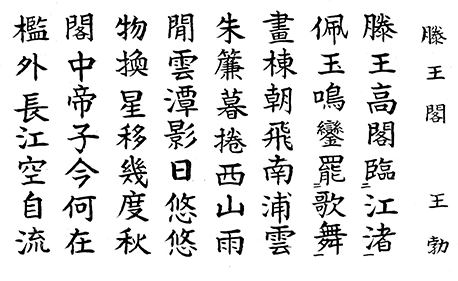
読み方
- 滕王閣<王勃>
- 滕王の高閣 江渚に臨み
- 佩玉鳴鑾 歌舞罷む
- 畫棟朝に飛ぶ 南浦の雲
- 朱簾暮に捲く 西山の雨
- 閒雲潭影 日に悠悠
- 物換わり星移る 幾度の秋ぞ
- 閣中の帝子 今何くにか在る
- 檻外の長江 空しく自ずから流る
- とうおうかく<おうぼつ>
- とうおうのこうかく こうしょにのぞみ
- はいぎょくめいらん かぶやむ
- がとうあしたにとぶ なんぽのくも
- しゅれんくれにまく せいざんのあめ
- かんうんたんえい ひにゆうゆう
- ものかわりほしうつる いくたびのあきぞ
- かくちゅうのていし いまいずくにかある
- かんがいのちょうこう むなしくおのずからながる
字解
-
- 滕王閣
- 唐代に滕王の建てた楼で今の江西省南昌県(こうせいしょうなんしょうけん)にあり、カン水(かんすい=江西省を流れ陽湖=はようこ=に注いでいる)に臨んでいる 岳陽楼・黄鶴楼とともに中国三大名楼といわれている
-
- 佩 玉
- 貴人が腰帯に下げる飾り玉
-
- 鳴 鑾
- 天子の車につけてある鈴
-
- 畫 棟
- 絵を画いたり塗ったりした美しい棟木(むなぎ)
-
- 南 浦
- 江西省南昌市にある船つき場となる入江
-
- 朱 簾
- 「朱」は珠(たま)に通ず たまの飾りをつけたすだれ たますだれ
-
- 閒 雲
- 静かに流れゆく雲
-
- 潭 影
- 水が深くよどむところ
-
- 帝 子
- 帝(みかど)の子
-
- 檻 外
- 手すりのそと
意解
滕王が建てたこの高閣は、カン水の渚を見下ろしてそそり立っている。滕王全盛の昔は多くの貴人が帯び玉や車の飾りの鈴音を鳴らして、人々は集まり、にぎやかに歌舞を楽しんだであろうが、今はそのようなことはなくなった。
画棟を用いた滕王閣に、朝ごと南浦の方から雲が飛び交い、夕べには珠の簾を捲き上げれば西山からの雨が眺められることであろう。
静かに流れゆく雲、淵にうつる物影は日ごとにゆったりとした姿を繰り返している。しかしながら、事物は移り変わり歳月も過ぎて、どれほどの秋を迎えたのであろう。
この高閣におられた滕王は、今どこにおられるのであろう。手すりのそとの、カン水は昔と変わらず空しく流れているだけである。
備考
この詩の構造は七言古詩の形であって、仄韻上声六語(ご)韻の渚、仄韻上声七麌(ぐ)韻の舞、雨の字が通韻として使われ、下平声十一尤(ゆう)韻の悠、秋、流の字が使われている。古詩のため平仄は論じない。「唐詩選」に所収されている。
作者略伝
王 勃 649-676
初唐の詩人。字は子安(しあん)、父は王福畤(おうふくじ)、祖父は王通(おうつう)といい学者の家の出である。山西省河津(かしん)県絳州(こうしゅう)龍門の人。幼時より詩文にすぐれ、20歳前に高宗の試問に応じ朝散郎(ちょうさんろう)の官をさずけられ、沛王府(はいおうふ)の修撰(しゅうせん)という職についた。のち高宗の怒りを買い蜀の国に流謫(るたく)される。父の王福畤も同時に交趾(こうち=今の北ベトナム)令(れい)に左遷された。王勃は大赦(たいしゃ)で出獄し、父を尋ねて南方に旅立ち、南海に落ちて死んだ。年28。
