漢詩紹介
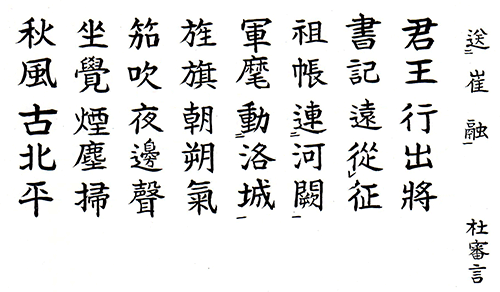
読み方
- 崔融を送る<杜審言>
- 君王行く 出でて將たり
- 書記 遠く征に從う
- 租帳 河闕に連なり
- 軍麾 洛城を動かす
- 旌旗 朝に朔氣
- 笳吹 夜邊聲
- 坐に覺ゆ 煙塵の掃うを
- 秋風 古の北平
- さいゆうをおくる<としんげん>
- くんのうゆくゆく いでてしょうたり
- しょき とおくせいにしたごう
- そちょう かけつにつらなり
- ぐんき らくじょうをうごかす
- せいき あしたにさくき
- かすい よるへんせい
- そぞろにおぼゆ えんじんのはろうを
- しゅうふう このほくへい
字解
-
- 君 王
- 則天武后(そくてんぶこう)の甥 武三思(ぶさんし)のこと
-
- 書 記
- 掌書記(しょうしょき) 元帥節度使府などにあって重要文書をあつかう役 崔融がそれにあたる
-
- 租 帳
- 旅立つ人の前途の平安を祈るため道の神を祭る時に用いる幕
-
- 河 闕
- 伊闕(いけつ)のこと 夏(か)の禹王(うおう)が伊水を疎通したとき両山相対していてこれを望むと闕(宮城の門)のようであったので伊闕という
-
- 軍 麾
- 軍を指揮する旗
-
- 朔 氣
- 北方の寒烈な気 「朔」は北方
-
- 笳 吹
- 胡笳の音
-
- 邊 聲
- 辺境の音色 ここでは胡笳の音
-
- 煙 塵
- 戦争のために生ずる殺気や塵埃(じんあい)
-
- 掃
- 賊軍を破り尽くす
-
- 古北平
- いにしえの右北平の地 今の北京一帯をいう
意解
武三思が勅命を受けて契丹(きったん)討伐の総大将として出陣するにあたり崔融は書記となって遠征に従った。
そこで盛大な壮行の宴が催され、その幕は伊闕にまで続き、将軍がひとたび采配をふるえば全軍の威勢は洛陽の城を動かすばかりである。
その軍勢が辺地に乗り込んで、朝は吹きすさぶ北風の寒さ、夜は遠くに聞こえる胡笳の音の悲しさ、それらの艱難辛苦はどれほどであろうか。
しかし大軍の行くところ、ちょうど秋風が煙塵を吹き掃うように夷狄(いてき)を破り尽くし、古よりの土地、北平一帯を奪還してめでたく凱旋されるであろう。
備考
この詩の構造は平起こり五言律詩の形であって、下平声八庚(こう)韻の征、城、聲、平の字が使われている。「唐詩選」に所収されている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
杜審言 648?-708
初唐の詩人、字は必簡(ひっかん)、襄陽(湖北省)の人。晋の名将で「左伝」の注者として名高い杜預(とよ)の子孫で、盛唐の大詩人杜甫の祖父として知られている。高宗の咸亨(かんこう)元年(670)の進士。隰城(しゅうじょう=山西省)の尉から洛陽(河南省)の丞(じょう)に転じたが罪を得て吉州(きっしゅう=江西省)の司戸(しこ)参軍に左遷された。則天武后の時代に召還されて著作佐郎、膳部員外郎を歴任したが、張易之(えきし)らの失脚にともない峰州(ベトナムのハノイ市付近)に流された。のち赦されて国土監主簿、修文館学士になった。武后朝を代表する詩人の一人で、李(りきょう)、崔融、蘇味道とともに文章の四友と称されたが、傲慢(ごうまん)な言動が多く人々に憎まれた。詩四十余首が現存し「杜審言集」があり、その大半が五言律詩。中宗皇帝の景龍2年に没す。
