漢詩紹介
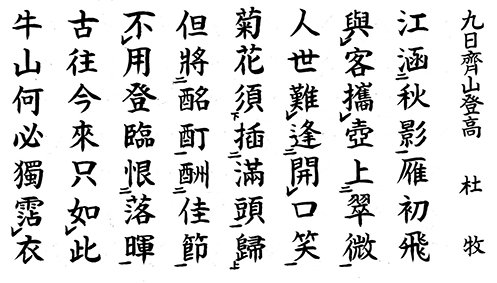
読み方
- 九日斉山に登高す <杜牧>
- 江は秋影を涵して 雁初めて飛び
- 客と壺を携えて 翠微に上る
- 人世口を開いて 笑うに逢い難く
- 菊花須らく 満頭に挿して帰るべし
- 但だ酩酊を将って 佳節に酬いん
- 用いず登臨して 落暉を恨むを
- 古往今来 只此くの如きのみ
- 牛山何ぞ必ずしも 独り衣を霑さんや
- きゅうじつせいざんにとうこうす <とぼく>
- こうはしゅうえいをひたして がんはじめてとび
- かくとつぼをたずさえて すいびにのぼる
- じんせいくちをひらいて わろうにあいがたく
- きっかすべからく まんとうにさしてかえるべし
- ただめいていをもって かせつにむくいん
- もちいずとうりんして らっきをうらむを
- こおうこんらい ただかくのごときのみ
- ぎゅうざんなんぞかならずしも ひとりころもをうるおさんや
語句の意味
-
- 九 日
- 高きに登る行事のある重陽節(ちょうようせつ=晩秋の9月9日)
-
- 斉 山
- 安徽省池州(ちしゅう)城の東南1・5㎞にある87メートルほどの山
-
- 翠 微
- 薄みどりの靄 山の中腹
-
- 人 世
- 塵世とも 俗世間
-
- 佳 節
- めでたい節句 9月9日の重陽の節句
-
- 登 臨
- 高所に登って低い所を見渡す
-
- 落 暉
- 夕陽の光
-
- 古往今来
- 古より今に至るまで
-
- 牛 山
- 山の名 現在の山東省淄博市(しはくし)南部にある
詩の意味
長江の流れは秋の影を宿し、雁が南へと渡り始めた。私は客人と酒壺を携えて、薄みどりの靄に包まれた斉山の中腹あたりまで登った。
俗世間では、大きく口を開いて愉快に笑えるようなことには、めったにあえない。せめてこの佳節を思う存分楽しみ、菊の花を頭にいっぱい挿して帰ろう。
そしてすっかり酒に酔って憂さを忘れ、このめでたい節句を祝うことにしよう。高所に登って沈む夕日を眺めても、悲しむ必要はない。
昔から今に至るまで人はこのように生き、このように暮らしてきたのであって、斉(せい)の景公(けいこう)のように、牛山に登って老いと死の訪れに涙を流すことはない。
出典
「三体詩」
備考
この詩は杜牧42歳の時の作。池州の長官をしていたころと思われる。
鑑賞
①「口を開いて笑はざる」の故事 「荘子(そうじ)」盗跖篇(とうせきへん)に「人は長生きできて100歳、中くらいなら80歳、そこそこでも60歳、病気や死、また悩みや憂いを除けば、そのうち口を開いて笑うことができるのは一か月で四、五日に過ぎない」とあるによる。
②「牛山に涙を流す」の故事 「列子」に「春秋時代(前5世紀)斉の景公が牛山に登って国見をした折、この美しい国土を残して死に切れないと嘆いた」話がある。臣下の晏子(あんし)は「もし人が死ななければ古代の聖賢天子が今も健在であり、王様の出る幕はありませんよ」と諫めた。
この二つの故事も含めて鑑賞したい。
参考
杜牧のこの詩によって斉山は一躍有名な詩跡となり、北宋の王安石や南宋の范成大、楊万里らによって次々と詠まれていく。そして山上には杜牧の詩にちなんだ「翠微亭」も造られた。
詩の形
平起こり七言律詩の形であって、上平声五微(び)韻の飛、微、帰、暉、衣の字が使われている。なお、七句目が二六不同になっている。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
杜牧 803~852
晩唐の政治家・詩人
号は樊川(はんせん)。京兆(けいちょう=今の西安)の名門の家に生まれ、若いころから詩文が得意で、23歳の時「阿房宮の賦」(あぼうきゅうのふ)を作り、その天才ぶりが世に知れ渡った。26歳で進士となり、江蘇省の楊州に赴任した時代には名作を多く残している。杜牧は美男子で歌舞を好み青楼に浮名(うきな)を流したこともあった。艶っぽい詩が多いけれど、半面その人柄は剛直で正義感に富み、大胆に天下国家を論じたりもした。33歳の時、中央政府の役人になるが、弟が眼病を患っていたので、弟思いの杜牧は自ら報酬の高い地方官を願い出て面倒を見た話はまた別の一面を語っている。中書舎人(ちゅうしょしゃじん)となって没す。享年50。「樊川文集」20巻、「樊川詩集」7巻がある。
