漢詩紹介
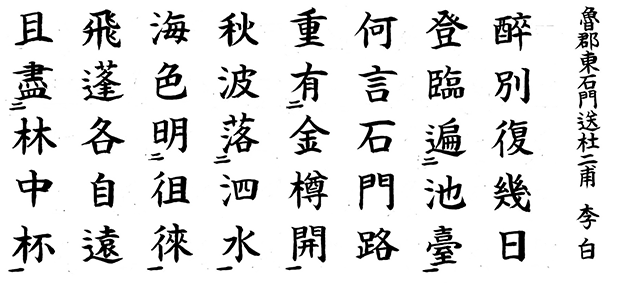
読み方
- 魯郡の東石門にて杜二甫を送る<李白>
- 酔別 復た幾日ぞ
- 登臨 池台に遍し
- 何ぞ言わん 石門の路
- 重ねて金樽の 開くこと有らんと
- 秋波 泗水に落ち
- 海色 徂徠に明らかなり
- 飛蓬 各自に遠し
- 且く 林中の 杯を尽くさん
- ろぐんのひがしせきもんにてとにほをおくる<りはく>
- すいべつ またいくにちぞ
- とうりん ちだいにあまねし
- なんぞいわん せきもんのみち
- かさねてきんそんの ひらくことあらんと
- しゅうは しすいにおち
- かいしょく そらいにあきらかなり
- ひほう かくじにとおし
- しばらく りんちゅうの はいをつくさん
語句の意味
-
- 魯 郡
- 今の山東省滋陽(じよう)県
-
- 石 門
- 今の山東省曲阜(きょくふ)県の東北にある山
-
- 杜二甫
- 杜甫 「二」は排行で一族の二番目の男子
-
- 登 臨
- 山に登って下方をのぞむ
-
- 池 台
- 池のほとりの高殿
-
- 金 樽
- 酒樽 「金」は美称
-
- 泗 水
- 山東省を流れる川 江蘇省の淮水(わいすい)に注いでいる
-
- 徂 徠
- 山東省泰安(たいあん)県の東南にある山 曲阜から東北にある
-
- 飛 蓬
- 風に飛ばされて漂うよもぎ 根なし草
詩の意味
別れを惜しんで酒に酔うことをもう幾日繰り返したことであろう。遠くを見はらすためあちこちの山に登り、下方をのぞみ、池のほとりの高殿も巡り尽くした。
これから別れる石門の道で、いつの日かふたたび金樽を開くことがあるなどと、どうして言えようか(もう君と会うこともなかろう)。
秋のさざ波は泗水の川面に立ち、東海のはてまで澄み切った秋の色は、徂徠山に明るく映えて美しい。
秋風に漂う根なし草のように、私も君も遠く離れ離れになってしまうのだから、今はただ、別れを惜しんで、林の中で杯を飲み干そうではないか。
備考
この詩は746年、李白46歳の時の作。送別する相手は33歳の杜甫である。実は2年前、二人は洛陽で初めて出会い、ともに旅に出て、最後に山東省一帯をめぐり石門山で別れる時に作られたものである。杜甫はこのころ科挙の試験に落第し、これといった官職にもありつけず、貧しい旅人であった。一方李白は玄宗に追放されたとはいえ、翰林供奉(かんりんぐぶ)として2年間玄宗皇帝に寵愛され、おそらく彼の詩人としての名声は杜甫の耳にも入っていたことだろう。その生活の程度の差こそあれ、二人は文学者として引きあうところがあった。
鑑賞
包容力のある李白が杜甫を感激させた
李白らしく酒で始まり(酔別)、酒でつなぎ(金樽開)、酒で締めくくっている(尽林中杯)。酒の匂いがしそうな詩である。酒こそが別れの悲しみを軽減させるものとして愛飲されたのだろう。
李白には年若いものを温かく迎える包容力がある。杜甫に対しては、その詩才を認めているから、なおさら濃い交遊である。杜甫は長い間一緒に旅までしてくれた彼の友情が嬉しかったのだろう。李白に対し15首もの詩を遺している。
詩の形
この詩は五言古詩であって、韻は上平声十灰(かい)韻の台、開、徠、杯の字が使われている。別に、律詩とみなす説もあるため、平仄を記す。
| 尾聯 | 頸聯 | 頷聯 | 首聯 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者略伝
李白 701~762
盛唐時代の詩人
四川省の青蓮郷(せいれんきょう)の人といわれるが出生には謎が多い。若いころ任侠の徒と交わったり、隠者のように山にこもったりの暮らしを送っていた。25歳ごろ故国を離れ漂泊しながら42歳で長安に赴いた。天才的詩才が玄宗皇帝にも知られ、2年間は帝の側近にあったが、豪放な性格から追放され、再び漂泊した。安禄山の乱後では反朝廷側に立ったため囚われ流罪となったが、のち赦され、長江を下る旅の途上で亡くなったといわれている。あまりの自由奔放・変幻自在の性格や詩風のためか、世の人は「詩仙」と称えている。酒と月を愛した。享年62。
