漢詩紹介
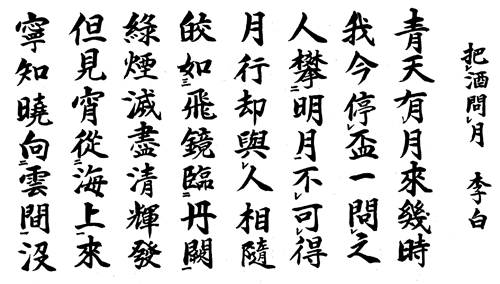
読み方
- 酒を把って月に問う(2-1)<李白>
- 青天月有って 來幾時ぞ
- 我今盃を停めて 一たび之に問う
- 人明月を攀ずること 得べからず
- 月行いて却って 人と相隨う
- 皎として飛鏡の 丹闕に臨むが如く
- 綠煙滅し盡きて 清輝發す
- 但見る宵に 海上從り來るを
- 寧んぞ知らんや曉に 雲間に向かって没するを
- さけをとってつきにとう<りはく>
- せいてんつきあって このかたいくときぞ
- われいまはいをとどめて ひとたびこれにとう
- ひとめいげつをよずること うべからず
- つきゆいてかえって ひととあいしたごう
- こうとしてひきょうの たんけつにのぞむがごとく
- りょくえんめっしつきて せいきはっす
- ただみるよいに かいじょうよりきたるを
- いずくんぞしらんやあかつきに うんかんにむかってぼっするを
字解
-
- 皎
- 白く光るさま
-
- 丹 闕
- 赤く塗った門 仙人の住む宮殿
-
- 綠 煙
- みどりのもや
意解
澄み切った青空、あの広い空にお月様はどれほどの年月いたのですか。私は今、盃の手を止めてちょっとお尋ねしたい。
人間は明月に攀じ登ることはできないが、反対にお月様の歩みは人間が歩くとどこまでもついてきてくれる。
お月様は白く光ってまるで空飛ぶ鏡が仙人の宮殿にさしかかったようで、夕暮れの碧のもやがすっかり消えると清らかな光が現れる。
人はただ夜になってお月様が海の方から昇ってくるのを見るだけで、明け方になって雲の間に沈んでいくのを知らない。
備考
この詩は「友人の賈淳(かじゅん)に月に問いかけてみよと勧められて作った」と李白自身の注にある。
詩の構造は七言古詩の形であって、四句一解で四解から成り、解ごとに換韻している。
第一解 上平声四支(し)韻の時、之、隨
第二解 入声六月(げつ)韻の闕、發、没
第三解 上平声十一眞(しん)韻の春、鄰、人
第四解 上声四紙(し)韻の水、此、裏
の字が使われている。
作者略伝
李 白 701-762
盛唐の詩人。杜甫(とほ)と並び称される。蜀(しょく)の錦州彰明県(きんしゅうしょうめいけん)青蓮郷(せいれんきょう)の人で青蓮居士(せいれんこじ)と号した。幼にして俊才、剣術を習い任侠の徒と交わる。長じて中国各地を遍歴し、42歳より44歳まで玄宗(げんそう)皇帝の側近にあり、のち再び各地を転々とし多くの詩をのこす。安禄山(あんろくざん)の乱に遭遇して、罪を得たがのち赦される。62歳病のため没す。
