漢詩紹介
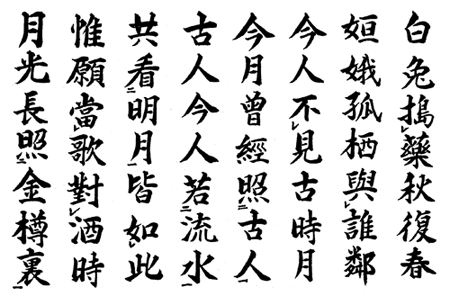
読み方
- 酒を把って月に問う(2-2)<李白>
- 白兔藥を搗く 秋復春
- 姮娥孤栖 誰と鄰せん
- 今人は見ず 古時の月
- 今月は曾て經たり 古人を照らすを
- 古人今人 流水の若く
- 共に明月を看て 皆此の如し
- 惟願う歌に當たり 酒に對するの時
- 月光長えに 金樽の裏を照らさんことを
- さけをとってつきにとう<りはく>
- はくとくすりをつく あきまたはる
- こうがこせい たれととなりせん
- こんじんはみず こじのつき
- こんげつはかつてへたり こじんをてらすを
- こじんこんじん りゅうすいのごとく
- ともにめいげつをみて みなかくのごとし
- ただねごううたにあたり さけにたいするのとき
- げっこうとこしえに きんそんのうちをてらさんことを
字解
-
- 白兔搗藥
- 中国の伝説に「月の中で兔が不老不死の薬を搗く」とある
-
- 姮 娥
- 古代神話の仙女 月の異名 嫦娥ともいう
意解
月の中では白兔が秋も春も不老不死の仙薬を臼で搗いていて、それを呑んだという仙女の姮娥は一人ぼっちで暮らし、誰が隣にいるだろうか、いや誰もいない。
今生きている人間は、昔のお月様を見ることができないが、今のお月様はずっと大昔から人々を照らし続けてきた。
昔の人も今の人もちょうど流れる水のようで、いつの時代の人々も明月を眺めては同じように去っていく。
お月さま、あなたにたった一つのお願いがある。私たちが歌を歌い酒を飲んでいる間は、どうかあなたの光でいつまでも黄金の酒樽の中を照らしてもらえまいか。
備考
この詩は「友人の賈淳(かじゅん)に月に問いかけてみよと勧められて作った」と李白自身の注にある。
詩の構造は七言古詩の形であって、四句一解で四解から成り、解ごとに換韻している。
第一解 上平声四支(し)韻の時、之、隨
第二解 入声六月(げつ)韻の闕、發、没
第三解 上平声十一眞(しん)韻の春、鄰、人
第四解 上声四紙(し)韻の水、此、裏
の字が使われている。
作者略伝
李 白 701-762
盛唐の詩人。杜甫(とほ)と並び称される。蜀(しょく)の錦州彰明県(きんしゅうしょうめいけん)青蓮郷(せいれんきょう)の人で青蓮居士(せいれんこじ)と号した。幼にして俊才、剣術を習い任侠の徒と交わる。長じて中国各地を遍歴し、42歳より44歳まで玄宗(げんそう)皇帝の側近にあり、のち再び各地を転々とし多くの詩をのこす。安禄山(あんろくざん)の乱に遭遇して、罪を得たがのち赦される。62歳病のため没す。
