漢詩紹介
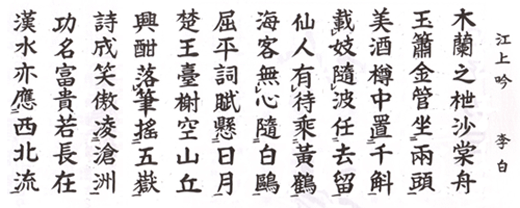
読み方
- 江上吟<李白>
- 木蘭の枻 沙棠の舟
- 玉簫金管 兩頭に坐す
- 美酒樽中 千斛を置き
- 妓を載せ波に随って 去留に任す
- 仙人待つ有って 黄鶴に乘じ
- 海客心無くして 白鴎に随う
- 屈平の詞賦は 日月を懸け
- 楚王の臺榭は 空しく山丘
- 興酣にして筆を落せば 五嶽を搖かし
- 詩成って笑傲すれば 滄洲を凌ぐ
- 功名富貴 若し長えに在らば
- 漢水も亦應に 西北に流るべし
- こうじょうぎん<りはく>
- もくらんのかい さとうのふね
- ぎょくしょうきんかん りょうとうにざす
- びしゅそんちゅう せんこくをおき
- ぎをのせなみにしたがって きょりゅうにまかす
- せんにんまつあって おうかくにじょうじ
- かいかくこころなくして はくおうにしたごう
- くっぺいのしふは じつげつをかけ
- そおうのだいしゃは むなしくさんきゅう
- きょうたけなわにしてふでをおとせば ごがくをうごかし
- しなってしょうごうすれば そうしゅうをしのぐ
- こうみょうふうき もしとこしえにあらば
- かんすいもまたまさに せいほくにながるべし
字解
-
- 木蘭之枻
- 枻(楫と同じ)は舟を進める道具 木蘭で作ったとはぜいたくな道具である
-
- 沙棠舟
- 崑崙山(こんろんざん)に生えるという珍木 それで作った舟は沈まないといわれた やはりぜいたくなもの
-
- 玉簫金管
- 簫も管も管楽器 それを宝玉や黄金で飾った立派なもの ここではそれを吹く楽人を指す
-
- 千 斛
- 斛は石(こく)と同じ ここではただ量の多いことを示すものとして使われている
-
- 海客無心随白鴎
- 列子(れっし)に見える寓話 かもめの好きな男があり 毎日浜辺でかもめと遊んだ ある日父親にそのかもめを捕まえて来いと言われて そのつもりで浜辺へ行くと その日に限ってかもめは一羽も寄って来なかった こちらが無心ならば相手も心をゆるすが 一たん邪念をおこせばすぐ先方に通じて失敗するという教訓
-
- 詞 賦
- 詞は辞と同じ 故に辞賦と書き 楚辞の系統の韻文の一型式を総称する
-
- 懸日月
- 天に太陽や月をかけたように 明るく光り輝く 史記屈原列伝に司馬遷(しばせん)が離騒に表現させた屈原のまごころをたたえて「日月と光を争うも可なり」と言っているのにもとづく
-
- 臺 榭
- 台を築きその上に建てた楼閣
-
- 五 嶽
- 大地のおさえとされる五つの名山 東は泰山(たいざん) 西は華山(かざん) 南は衡山(こうざん) 北は恒山(こうざん) 及び中央は嵩山(すうざん)をいう
-
- 滄 洲
- 中国から数万里の海中にあって 仙人が住むといわれる島 不老不死の楽園をいう
-
- 漢 水
- 陝西省(せんせいしょう)から出て湖北省を東南に流れ 武昌で揚子江に合流する川 それが西北に流れるとは全くありえないことをいう
意解
わが乗るは、木蘭のかいをそなえ、沙棠で作ったみごとな舟。
舟中の両側には玉で飾った簫と黄金で飾った笛を持つ女たちがいならぶ。樽の中には千石もの美酒をたたえ、妓女をのせ、波のまにまに、行くも止まるも流れにまかせたまま。
俗世を超越した仙人でも、何かをあてにしなければならぬ。それは黄鶴に乗ることだ。だが私はあの海辺の人のように、無心の境地で白鴎の群に随って遊ぶ(その自由さが、何よりもうれしい)。
屈原の詞賦は天空に日月をかかげたかと思われるばかり。今もその輝きを失わないが、当時の権勢をほこった楚王の豪奢な楼閣は、今はむなしく山や丘を残すばかりで、あとかたもない。
興のつのるままに筆をおろして、わが詩を書きつければ、その壮大な気宇(心のひろさ)に五岳も揺れ動くほど。詩をかきあげて得意の高笑いをすれば、不老不死の楽園という滄洲の島も何のその。
この世の功名だの富貴だのと言うものが、もしも永遠に存続し得るとすれば、東南に流れている漢水がなんと西北に向って流れることだろう。
四句宛に分けて三解とする。
備考
この詩の構造は七言古詩の形であって、下平声十一尤(ゆう)韻の舟、頭、留、鴎、丘、洲、流の字が使われて いる。一韻到底格の詩である。
作者略伝
李白 701-762
盛唐の詩人。杜甫と並び称される。蜀(しょく)の錦州彰明県(きんしゅうしょうめいけん)青蓮郷(せいれんきょう)の人で青蓮居士(せいれんこじ)と号した。幼にして俊才。剣術を習い任侠の徒と交わる。長じて中国各地を遍歴し、42歳より44歳まで玄宗(げんそう)皇帝の側近にあり、のち再び各地を転々とし多くの詩をのこす。安禄山(あんろくざん)の乱に遭遇して罪を得たがのち赦される。62歳病のために没す。
