漢詩紹介
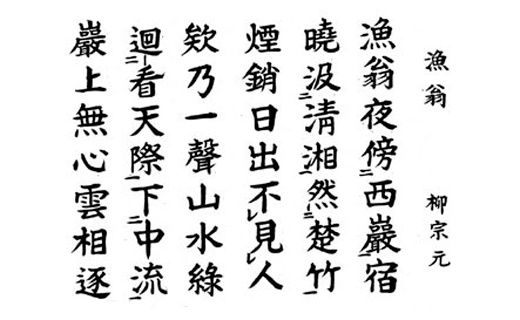
読み方
- 漁翁<柳宗元>
- 漁翁 夜 西巖に傍いて宿し
- 暁に淸湘に汲みて 楚竹を然く
- 煙銷え日出でて 人を見ず
- 欸乃一聲 山水綠なり
- 天際を迴看して 中流を下れば
- 巖上無心に 雲相逐う
- ぎょおう<りゅうそうげん>
- ぎょおう よる せいがんにそいてしゅくし
- あかつきにせいしょうにくみて そちくをたく
- けむりきえひいでて ひとをみず
- あいだいいっせい さんすいみどりなり
- てんさいをかいかんして ちゅうりゅうをくだれば
- がんじょうむしんに くもあいおう
字解
-
- 汲淸湘
- 清らかな湘江(その水)をくむ
-
- 然楚竹
- 楚竹は楚の地方に多い篠竹(しのだけ)の類 ここではそれを燃やして朝食を準備する 然は燃と同じ
-
- 煙 銷
- もやが晴れて 銷は消と同じ
-
- 欸 乃
- 舟をこぐかけ声 一説に櫓のきしむ音 又は舟歌
-
- 無心雲相逐
- 雲が無心に追いかけあっているように流れていた この句の雲は自由自在であり漁翁も又孤高の隠士になぞらえる 更にそれは詩人の平静淡白の心情に通ずる無心である
意解
年老いた漁師が、夜になると、西岸の大きな岩に舟を寄せて停泊した。明け方に彼は清らかな湘江に水をくみ、楚の竹を燃やして朝食を作る。
やがてもやが晴れ太陽が昇ると、もはや漁翁の姿は見あたらない。舟をこぐかけ声がひと声高くひびいて、山も水もあたりはすべて緑一色に染まっている。
空の果てを遠くふり返りつつ、川の中ほどを下って行くと、雲が大岩の上空に、無心に追いかけあっているように流れていた。
備考
この詩の構造は七言古詩六句形式で、入声(にっしょう)一屋(おく)韻の宿、竹、逐と二沃(よく)韻の綠の 字が使われている。
作者略伝
柳宗元 773-819
中唐の文書家、詩人。字は子厚(しこう)。唐宋八大家の一人。諸官を経て柳州の刺史(漢、唐代の州の長官)で終り、同地に没す。
