漢詩紹介
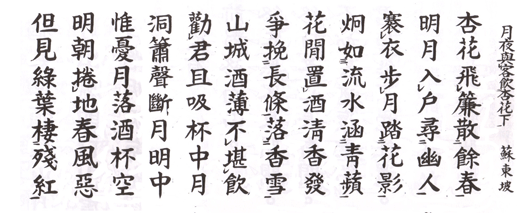
読み方
- 月夜客と杏花の下に飲む<蘇東坡>
- 杏花簾に飛んで 餘春を散ず
- 明月戸に入りて 幽人を尋ぬ
- 衣を褰げ月に歩して 花影を踏めば
- 炯として流水の 青蘋を涵すが如し
- 花閒に酒を置けば 清香發し
- 爭でか長條を挽きて 香雪を落とさん
- 山城酒薄く 飲むに堪えざらん
- 君に勸む且く吸え 杯中の月
- 洞簫聲は斷ゆ月明の中
- 惟だ憂う月落ちて 酒杯の空しからんを
- 明朝地を捲いて 春風惡しくば
- 但だ見ん綠葉の 殘紅を棲ましむるを
- げつやきゃくときょうかのもとにのむ<そとうば>
- きょうかれんにとんで よしゅんをさんず
- めいげつこにいりて ゆうじんをたずぬ
- いをかかげつきにほして かえいをふめば
- けいとしてりゅうすいの せいひんをひたすがごとし
- かかんにさけをおけば せいこうはっし
- いかでかちょうじょうをひきて こうせつをおとさん
- さんじょうさけうすく のむにたえざらん
- きみにすすむしばらくすえ はいちゅうのつき
- どうしょうこえはたゆ げつめいのうち
- ただうれうつきおちて しゅはいのむなしからんを
- みょうちょうちをまいて しゅんぷうあしくば
- ただみんりょくようの ざんこうをすましむるを
字解
-
- 幽 人
- 世を捨て隠れ住んでいる人 隠者
-
- 褰 衣
- 水を渡る時衣のすそを濡れないようにからげる動作
-
- 炯
- 明らかなさま
-
- 涵青蘋
- 水草をひたす
-
- 爭
- どうして どのように
-
- 長 條
- 木の長い枝
-
- 香 雪
- 白い花の形容 ここでは杏の花をさす
-
- 山 城
- 山にある町 いなかの町
-
- 洞 簫
- 管楽器 尺八に似た竹製の吹奏楽器
-
- 捲 地
- 大地の砂塵をまきあげる強い風の吹くさま
-
- 殘 紅
- 散り残っている赤い花
意解
すだれにはらはらとふりかかる杏の花びらに、のこりの春の散らされてゆく今宵ー、戸口からさしこむ明月が、世をわびて住まう主のまろうどとなった。庭に歩み出た私は、思わず衣のすそをかかげて、地上にちらついている花影の中に踏みこんだ。その影はあまりにくっきりと鮮かで、青いうきぐさが、流水のひたひたとよせる波にもてあそばれているさま、さながらであったからである。
杏の樹の花かげに酒を汲めば、酒から清らかな香りが漂ってくる。なにも杏の樹の長い枝を手でたわめて、香りたかい雪のような花弁を杯中に落すことはない。それにしても山あいのまちの酒はうすくてお口にあうまいから、君にはまあ杯中の月を飲んでいただこう。
(洞簫を吹いていた兄弟も杯をとった)洞簫の音がぴたっとやんだ。あとに残るのは、しらじらとさえわたる月光ばかり。そうだ、いずれ月も落ち酒杯も傾けつくすときがくる。その時味わわねばならぬ空しさが今から気がかりだ。明朝、春につきもののいとわしい強風が、砂塵をまきあげて吹きまくるなら、この杏の樹ももう、散り残った紅の花が、いきおいのよい緑の葉の中に、遠慮ぎみにすみかを与えられているにすぎないであろう。
備考
この詩の構造は七言古詩の形であって、押韻は1~4句まで上平声十一真(しん)韻の春、人、蘋、5~8句は入 声(にっしょう)六月(りくげつ)韻の發、月、九屑(せつ)韻の雪、9~12句は上平声一東(とう)韻の中、空、紅の字が使われている。
詩題は「月夜與客飲酒杏花下」として酒の字を加えているものも有る。
この詩は、作者が元豊(げんぽう)2年(1079)の春、徐州にいた時の作で、蘇東坡の官舎に寄寓していた王子立(おうしりつ)・王子敏(おう しびん)の兄弟と、蜀から来た客の張師厚(ちょうしこう)の3人とともに、春の夜、花間で酒盛りをしたことを歌ったもの。
作者略伝
蘇東坡 1036-1101
北宋第一の詩人、名は軾(しょく)、字は子瞻(しせん)、東坡は号。父洵(じゅん)、弟轍(てつ)と共に 文学者にして三蘇といわれた。四川省眉山(びざん)県紗穀行(さこくこう)の生まれ。幼にして 道教的教育をうけ、上京して官途につく。中央、地方の官を歴任しその間度々流謫(るたく)された。 官は礼部尚書(れいぶしょうしょ)に至る。江蘇省常州において没す。死後、文忠公(ぶんちゅうこう)と諡 (おくりな)される。
