漢詩紹介
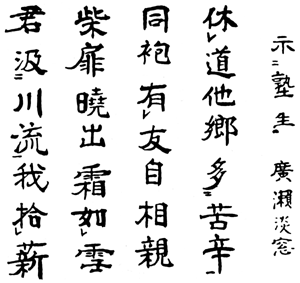
CD①収録 吟者:松野春秀
2014年5月掲載
読み方
- 塾生に示す<広瀬淡窓>
- 道うことを休めよ他郷 苦辛多しと
- 同袍友有り 自ずから相親しむ
- 柴扉暁に出ずれば 霜雪の如し
- 君は川流を汲め 我は薪を拾わん
- じゅくせいにしめす<ひろせたんそう>
- い(ゆ)うことをやめよ たきょう くしんおおしと
- どうほうともあり おのずからあいしたしむ
- さいひあかつきにいずれば しもゆきのごとし
- きみはせんりゅうをくめ われはたきぎをひろわん
詩の意味
塾生たちよ、遠く他郷にあって勉学に励むのが辛(つら)いなどということはやめなさい。一枚の綿入れをいっしょに着あうような新しい友もでき、自然に親しみあっていけるのだ。
朝早く、粗末な扉を開いて外に出ると、霜が一面に降りてまるで雪のようだ。さあ、朝食の支度にとりかかろう。君は川に行って水を汲んできたまえ、私は薪を拾ってくるから。
鑑賞
励まし合った桂林荘の塾生
本題は「桂林荘雑詠諸生に示す(其の二)」と言います。桂林荘とは、江戸末期に今の大分県の日田(ひた)市に淡窓が開いた私塾です。
他郷にあっての学問修行は辛いことではあるが、学友たちと共に苦労するなかにこそ格別の楽しみもあるということを述べ、塾生たちを励ましているのです。
語句の意味
-
- 塾 生
- 塾で学ぶ生徒 広瀬淡窓の塾を桂林荘という
-
- 同 袍
- 「袍」は綿入れの上着 それを互いに貸し合って着るほどの親しい仲間
-
- 柴 扉
- 柴で作った粗末な戸
備考
広瀬淡窓は、亀井南溟(なんめい)に学び24歳にして私塾「桂林荘」を開き、後に「咸宜園(かんぎえん)」と改名した。淡窓の名を慕って全国64カ国の各藩から集まった塾生は4617人に及んだ。「咸宜園」においては、入学式に際し新旧学生の紹介式で塾歌を吟詠し、学舎吟または正風吟と称して詩の正しい吟詠法として地方に伝吟し、「咸宜園流」の名が広まった。
詩の形
仄(そく)起こり七言絶句(しちごんぜっく)の形であって、上平声(じょうひょうしょう)十一眞(しん)韻の辛(しん)、親(しん)、薪(しん)の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
広瀬淡窓 1782-1856
江戸後期の学者・漢詩人
大分県日田市の商人の家に生まれる。16歳で福岡に出て学問修行に励んだ。18歳で故郷に帰り24歳で塾を開いた。これを「桂林荘」という。さらに発展させ「咸宜園」と名を変えた。その盛んなことは九州第一であり、大村益次郎をはじめ多くの逸材を育てた。長年の育英の功績により名字帯刀を許され、また正五位を賜った。享年75歳。
