漢詩紹介
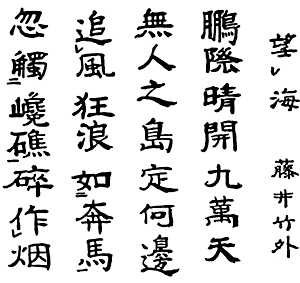
吟者:中島菖豊
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 海を望む <藤井 竹外>
- 鵬際晴れ開く 九万の天
- 無人之島は定めて 何れの辺なる
- 風を追う狂浪 奔馬の如く
- 忽ち巉礁に触れて 砕けて煙と作る
- うみをのぞむ <ふじい ちくがい>
- ほうさいはれひらく きゅうまんのてん
- むじんのしまはさだめて いずれのへんなる
- かぜをおうきょうろう ほんばのごとく
- たちまちざんしょうにふれて くだけてけむりとなる
詩の意味
鵬(おおとり)のかけめぐる大空は晴れわたっていて、海は果てしなく広く望まれる。かねて聞いていた無人島というのはどのあたりにあるのだろうか。島は見えないが、多分あのあたりにあるのであろう。
海上に、遠くの沖から風に乗って狂い寄せる波は、まるで奔馬のような勢いで寄せてきて、たちまち険しい岩島にぶつかり、砕け散って煙となって飛び散る、まことに壮快な眺めである。
語句の意味
-
- 鵬 際
- 鵬の飛び翔ける大空
-
- 九万天
- 九万里の天 広大な大空
-
- 狂 浪
- 激しく荒れ狂う波
-
- 奔 馬
- 暴れ馬 勢いのよいたとえ
-
- 巉 礁
- 「巉」は切り立って険しいさま 「礁」は水面に見え隠れする岩
鑑賞
太平洋の勇猛さを描写した叙景詩
まるで映画の1シーンを見るようで、広大でかつ荒々しく、男性的な大海が手に取るように描かれている。怒涛(どとう)の音が聞こえるような迫力がある。叙景詩の典型である。ただ太平洋は常に荒れ狂っているわけではないので、この詩はあるいは台風の折の光景とも考えられるが、それもまた一面の趣きである。
漢詩の小知識
鵬とはどんな鳥
どれくらい大きいのかな。戦国時代の「荘子(そうじ)」という本に次のような記述がある。「北冥(ほくめい=北の果てにある大海)に魚あり、その名を鯤(こん)となす。鯤の大なることその幾千里なるかを知らず。化して鳥となり、その名を鵬となす。鵬の背はその幾千里なるかを知らず。怒して飛べば、その翼は垂天の雲のごとし。この鳥や、海の動くとき、則ちまさに南冥(なんめい=南の果てにある海)に移らんとす。南冥とは天池なり」と。
つまりひと飛びかふた飛びで地球を駆け抜けるという想像上の大きな鳥である。
参考
太平洋を歌うもう一つの詩
太平洋を詠じた詩は本会採用では吉田松陰の「磯原客舎」や頼鴨厓の「起坐」などがあるが、これらは尊王思想を鼓舞するための背景として描かれている。無色不偏の詩では安達漢城の「太平洋上作有り」がいい。もう一つ、三島中洲の「磯浜望楼に登る」がある。
夜登る百尺海湾の楼 極目何れの辺か是れ米州
慨然忽ち発す遠征の志 月は白し東洋万里の秋
果てしない太平洋の向こうにアメリカという国がある。行ってみたいと歌う。明治初期の多くの日本人の憧れが素直に詠じられている。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、下平声一先(せん)韻の天、辺、煙の字が使われている。
平仄
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
藤井 竹外 1807~1866
江戸末期の漢詩人
文化4年摂津高槻藩(大阪府高槻市)の名家に生まれる。名は啓(けい)、字は士開(しかい)、号は竹外または雨香仙史(うこうせんし)という。頼山陽に学び、梁川星巖、広瀬淡窓などと交わる。絶句に秀で「絶句竹外」の称あり。生涯酒と詩を好んだ。多くの詩篇を遺す。吉野の如意輪寺に「芳野懐古」の真筆がある。慶応2年没す。享年60。
