漢詩紹介
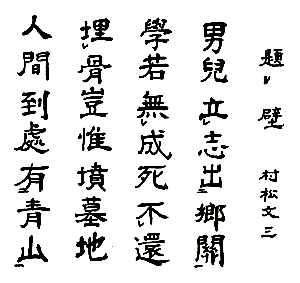
吟者:辰巳快水
2011年1月掲載[吟法改定再録]
読み方
- 壁に題す <村松 文三>
- 男児志を立てて 郷関を出ず
- 学若し成る無くんば 死すとも還らず
- 骨を埋む豈惟 墳墓の地のみならんや
- 人間到る処に 青山有り
- へきにだいす <むらまつ ぶんぞう>
- だんじこころざしをたてて きょうかんをいず
- がくもしなるなくんば しすともかえらず
- ほねをうずむあにただ ふんぼのちのみならんや
- にんげんいたるところに せいざんあり
詩の意味
男子がひとたび志を立てて故郷を出るからには、学問がもし成就(じょうじゅ)しないならば、死んでも故郷に帰らないつもりだ。
自分の骨を埋めるのは、何も故郷の墓地に限ったことではない。世の中にはどこへ行っても自分の骨を埋めるのにふさわしい青々とした美しい山があるではないか。
語句の意味
-
- 題 壁
- 作者が郷里を発するに際し志を壁に書きつける
-
- 郷 関
- 故郷
-
- 墳墓地
- 先祖代々の墓のある所 生まれ故郷
-
- 人 間
- 世の中
-
- 青 山
- 青々とした美しい山 墓地 蘇東坡の詩「是処青山可埋骨」に基づく
鑑賞
男児たるもの名をあげてこそ男の本懐
この詩は作者が15歳で故郷伊勢を出るとき、自分の固い決意を書きつけたもの。思いを壁に書きつけることは中国文人の習慣である。一読してその趣旨はわかる。いささか教訓めいていて堅苦しい。こういう類の詩は中国にはあまりないので、いかにも日本人好みといえる。男児たるもの名を挙げてこそ男の本懐という時代にふさわしい作である。風情や情緒はないが、強い精神がみなぎっている。特に第三句の「豈惟……」は文法的には反語形といわれ、基本的には「どうしてただ……だけであろうか、大切なことは他にもある」と表現したい時に用いる句法である。凡人なら最後は故郷に帰って先祖の墓でも守っていきたいというところだが、偉人はそうではない。勇気づけられる詩である。
備考
その1
結句の「人間」を「にんげん」と読むか「じんかん」と読むかによって解釈は異なる。現代では「にんげん」と読んで一つの精神、人格を持った人を指して用いる。「じんかん」は李白の「山中問答」に「人間に非ざる有り」とあるように、俗世間とか、この世を意味する。教本では「にんげん」と訓読しながら詩の意味は「じんかん」を採用している。
その2
作者に異説がある。同時期で交際のあった僧 釈月性(号は清狂)が27歳の時、大阪に遊学するに際して詠んだというもの。月性の「清狂吟稿」には「将に東遊せんとして壁に題す 二首」とあってこの詩が併記されているが、本会では宮崎東明先生の検証により村松文三の作とした。
漢詩の小知識
漢字の読み方によって意味が異なるもの
-
- 人間
- にんげん=人格を持った人 じんかん=世間(の人)
-
- 四時
- よじ=時刻を表す しじ=春夏秋冬
-
- 小人
- こびと=体格の小さい人 しょうじん=つまらぬ人
-
- 一人
- ひとり=人を数える単位 いちにん=君主
-
- 百姓
- ひゃくしょう=農夫 ひゃくせい=人民
-
- 包丁
- ほうちょう=刃物 ほうてい=料理人
-
- 大人
- おとな=成人 たいじん=徳の高い人
詩の形
平起こり七言絶句の形であって、下平声十五刪(さん)韻の関、還、山の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
村松文三 1828~1884(1874説あり)
江戸後期の医者・政治家・漢詩人
幸崎管仲(こうさきかんちゅう)の子。伊勢(三重県)山田の人。名は文三、号は香雲、二十回狂士。 駿河の国(静岡県)焼津の村松玄庵に医を学び、養子となる。性格は慷慨(こうがい)勤皇の志が厚く、賴三樹三郎、 橋本左内らと志を通じ国事に奔走した。維新後、福岡県令となり明治17年に没す。享年57。特旨を以て正五位を贈られる。
