漢詩紹介
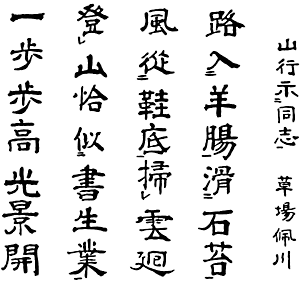
読み方
- 山行同志に示す <草場 佩川>
- 路は羊腸に入りて 石苔滑らかなり
- 風は鞋底従り 雲を掃うて廻る
- 山に登るは恰も 書生の業に似たり
- 一歩 歩 高くして 光景開く
- さんこうどうしにしめす <くさば はいせん>
- みちはようちょうにいりて せきたいなめらかなり
- かぜはあいていより くもをはろうてめぐる
- やまにのぼるはあたかも しょせいのぎょうににたり
- いっぽ ほ たかくして こうけいひらく
詩の意味
山路は羊の腸のようにくねくねと曲がり、苔の生えた石は滑らかで、風は足もとから雲を払って吹きめぐる。
さて、山に登るのはちょうど書生の学問修業と同じで、一歩高い所に登るにつれて、新しい視界が開けてくる。
語句の意味
-
- 羊 腸
- 羊の腸のように山道が曲がりくねって険しいようす
-
- 鞋 底
- 「鞋」はわらじ 足もと
-
- 光 景
- 景色
鑑賞
書生の修業も登山と同じ
この詩は、学問が上達するにしたがい、その道に限らず、世間一般に対しても視野が開け、凡人の味わい得ない壮快さを得られるようになるということを山登りに託して説いている。この発想は決して珍しいものではない。たとえば「学問の道は山のごとし、いよいよ登ればいよいよ高し」などの名言がある。ただどちらかといえば学問修業は苦渋に満ちてとらえられている場合が多い。勧学の代表詩のように言われる朱熹の「偶成」には「少年老い易く学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず」とか、陶淵明の「勧学」には「時に及んで将に勉励すべし、歳月は人を待たず」など、学問は苦しく厳しい修業であると叱咤(しった)しているのが通例だが、佩川の詩はそこを一歩出て、学問をすればするほど視野が開け、より高度な世界に入ることができるというのだから、前向きで明るい希望を抱かせる。ただ修業せよというだけでは滅入ってしまう。作者は晩年に藩(佐賀)校の教授をしたというから、そこの学生に与えた詩かもしれない。わかりやすく励みになる日本人好みの名詩である。
備考
1句目の「滑石苔」は語順が漢文調でない。石苔が滑らかなりという意味だから本来なら「石苔滑」とならなくてはならない。しかし起句の終わりに灰音の韻字が欲しい場合は、意味を変えない程度で、語順を変えることがある。
詩の形
仄起こり七言絶句の形であって、上平声十灰(かい)韻の苔、廻、開の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
草場佩川 1787~1867
江戸後期の医者・儒学者・教育者・詩人
佐賀藩の人。名を鞾(い、あきら)、字を棣芳(ていほう)、佩川はその号。天明7年、肥前の国(佐賀県)多久に生まれる。若くして江戸に出て古賀精里に学び、学成り、帰郷して儒官となる。菅茶山、篠崎小竹、頼山陽等と交わる。多種多芸にして、武芸はもとより和歌、篆刻(てんこく)、雅楽、南画等にも長じていたという。詩は多作にして2万首に及んだ。慶応3年没す。享年80。従四位を追贈される。
