漢詩紹介
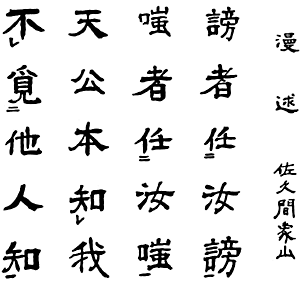
CD4収録 吟者:山口華雋
2015年12月掲載
読み方
- 漫 述 <佐久間 象山>
- 謗る者は汝の 謗るに任す
- 嗤う者は汝の 嗤うに任せん
- 天公本 我を知る
- 他人の 知るを覓めず
- まんじゅつ <さくま しょうざん>
- そしるものはなんじの そしるにまかす
- わろオものはなんじの わろオにまかせん
- てんこうもと われをしる
- たにんの しるをもとめず
詩の意味
私を非難する者もまた嘲(あざけ)り笑う者も、ともに諸君の意に任せよう。
天はもとより私のことを知ってくれているから、他人から認められようなどとは思ってもいない。
語句の意味
-
- 漫 述
- 「漫」はそぞろに 思いつくまま述べる
-
- 謗
- 非難する
-
- 嗤
- 冷笑 嘲り笑う
-
- 天 公
- 天の神 お天とうさま
鑑賞
お天とう様のみ知っている象山の思想とは
表面的な歌旨は一読すれば文字通りで承知できる。つまり「あざ笑うものは笑うがよい、お天とうさまは私の真意をお見通し」と豪語している。
ではその象山の信念とは何だろう。彼は長野県松代藩士で、若くして儒学および洋学を学んだ人である。彼の政治思想を表すなら「公武合体論」「開港論」「開国論」などさまざまであろうが、一言で言うなら「開国論者」である。1840年アヘン戦争で、中国の一部がイギリスの属国になったことに強い衝撃を受け、日本も思想の方向を変えなければ中国の二の舞になると強い危機感を持って行動した人である。だから「他人の知るを覓めず」なのである。この人たちの思想が日本を植民地から救ったともいえる。そういう崇高な思想が根底にあるから、この詩の一語一語がずしん、ずしんと胸に響いてくるのである。
参考
「時にあはば 散るもめでたし 山桜
愛ずるは花の さかりのみかは」
という自己の死を惜しむような和歌を残している。
また長野県松代町象山に「象山神社」がある。地元では「ぞうざん」と呼ばれている。
詩の形
二・四不同の作詩上の規則が守られていないので、五言古詩の形であって、上平声四支(し)韻の嗤、知の字が使われている。
| 結句 | 転句 | 承句 | 起句 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
作者
佐久間象山 1811~1864
江戸末期の思想家・開国論者
文化8年、信州(長野県)松代に生まれる。名は啓(ひらき)、字は子明(しめい)、象山は号である。16歳で鎌田桐山(とうざん)の門に入り、江戸に出て佐藤一斉に師事し、自らも神田お玉ケ池に「象山書院」あるいは「五柳精舎」を興す。常に国家の安危を憂い、国事に奔走した。公武合体、開国論を主張したので尊王攘夷派から敵視され、元治元年7月刺客のために斃(たお)れる。享年54。吉田松陰はその門下生である。
